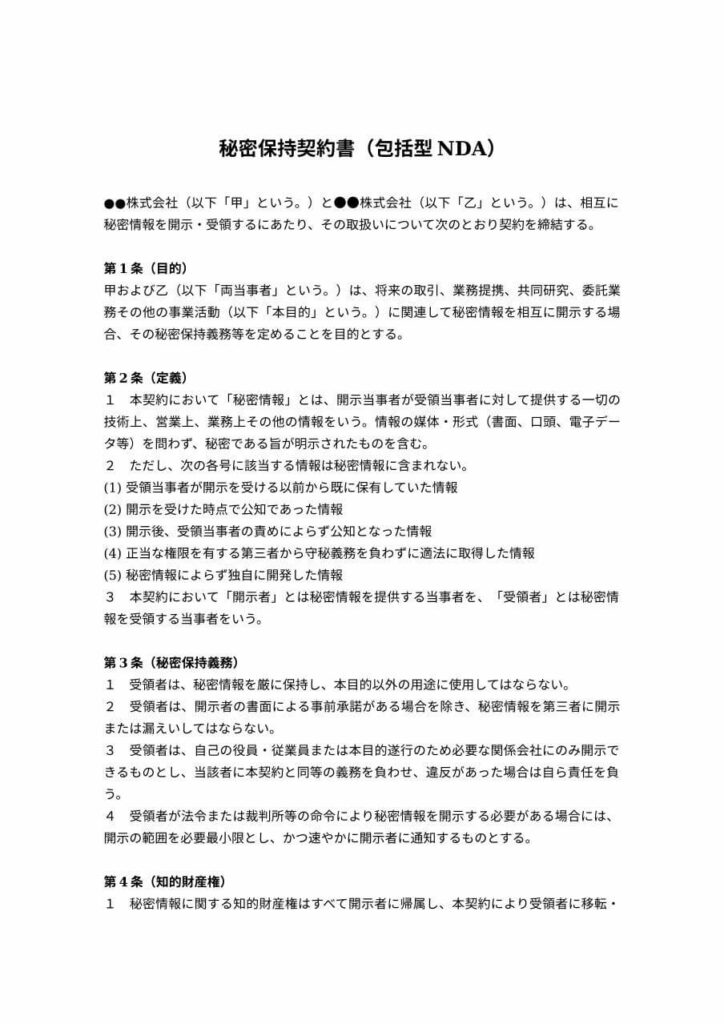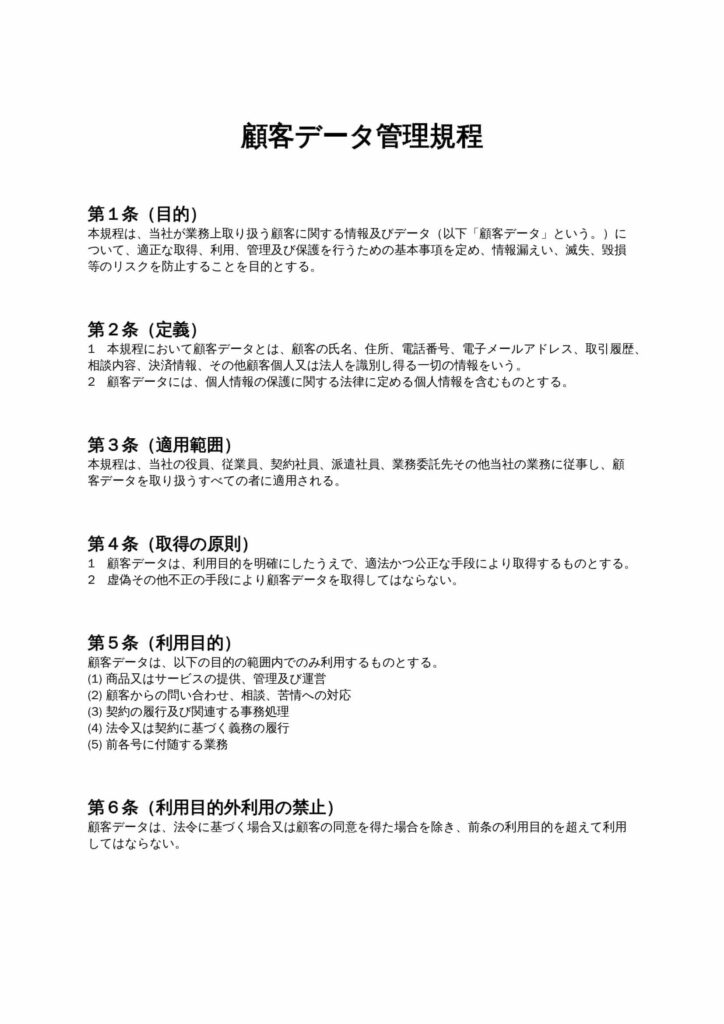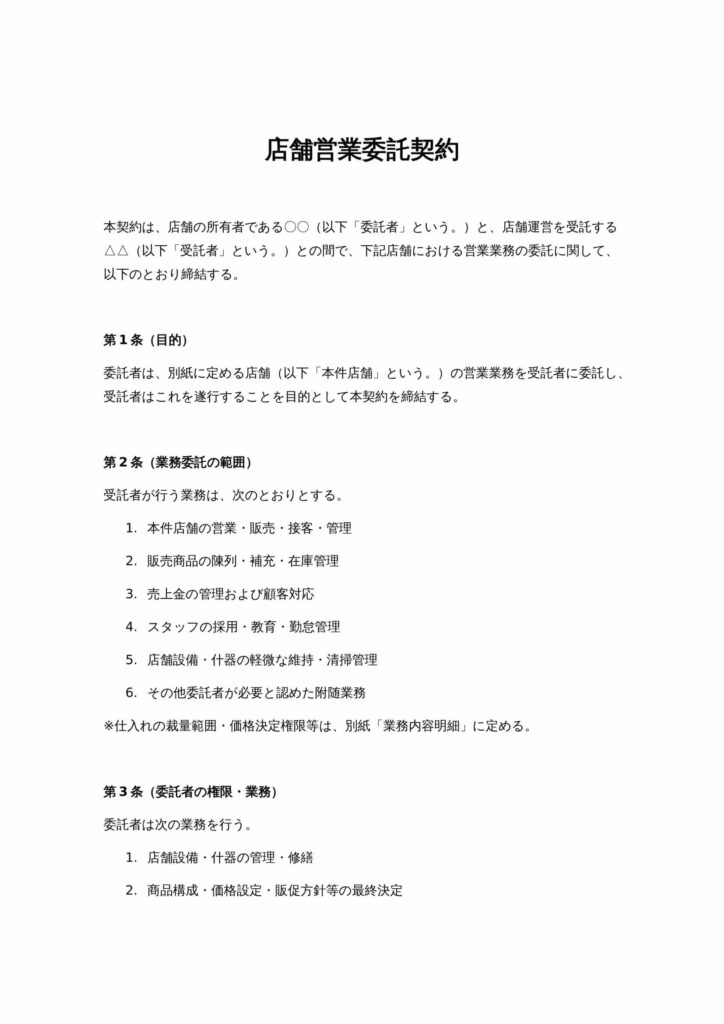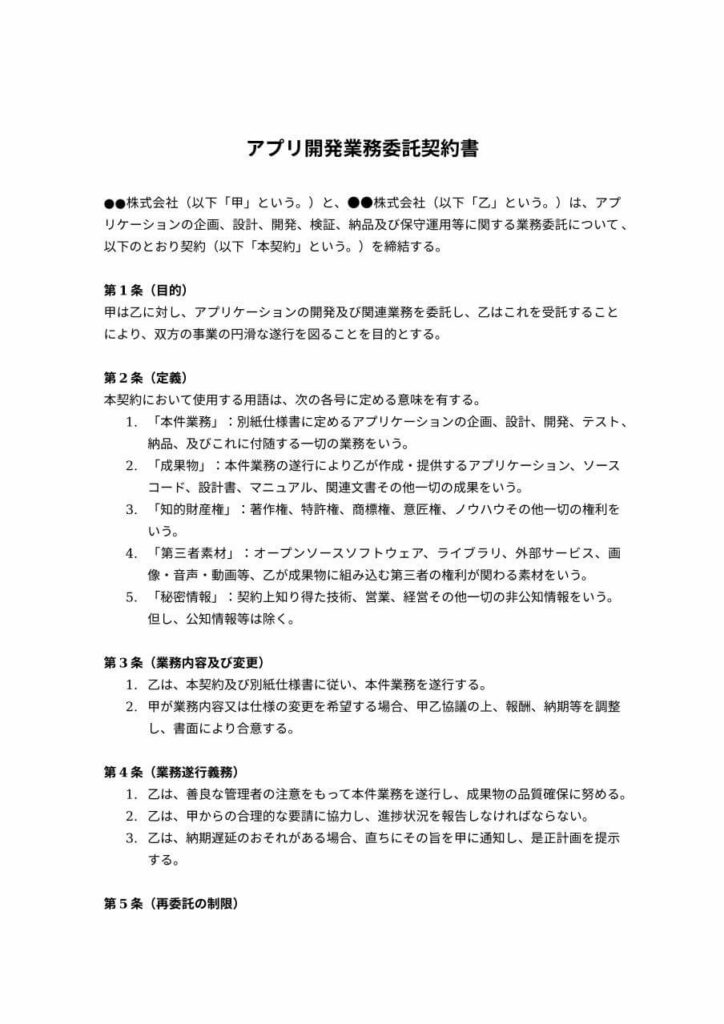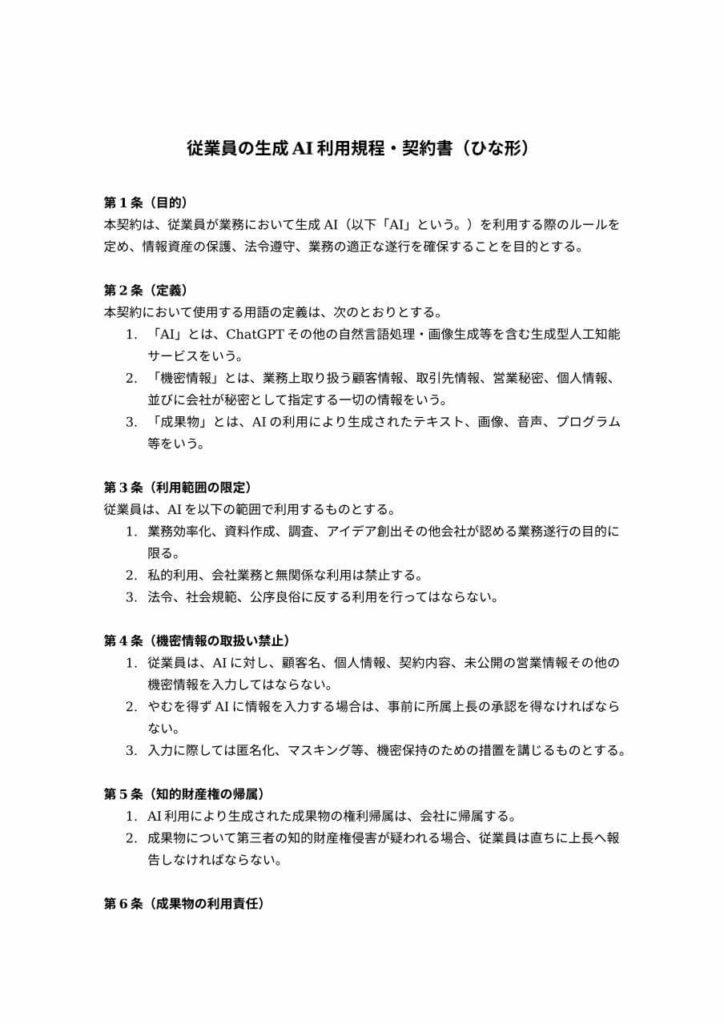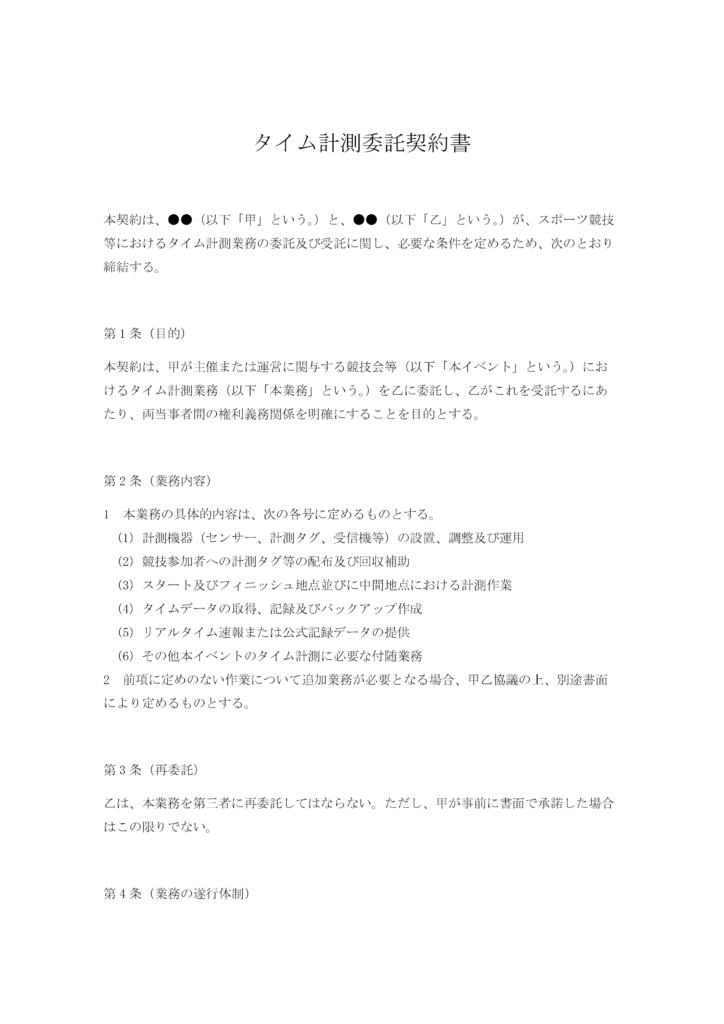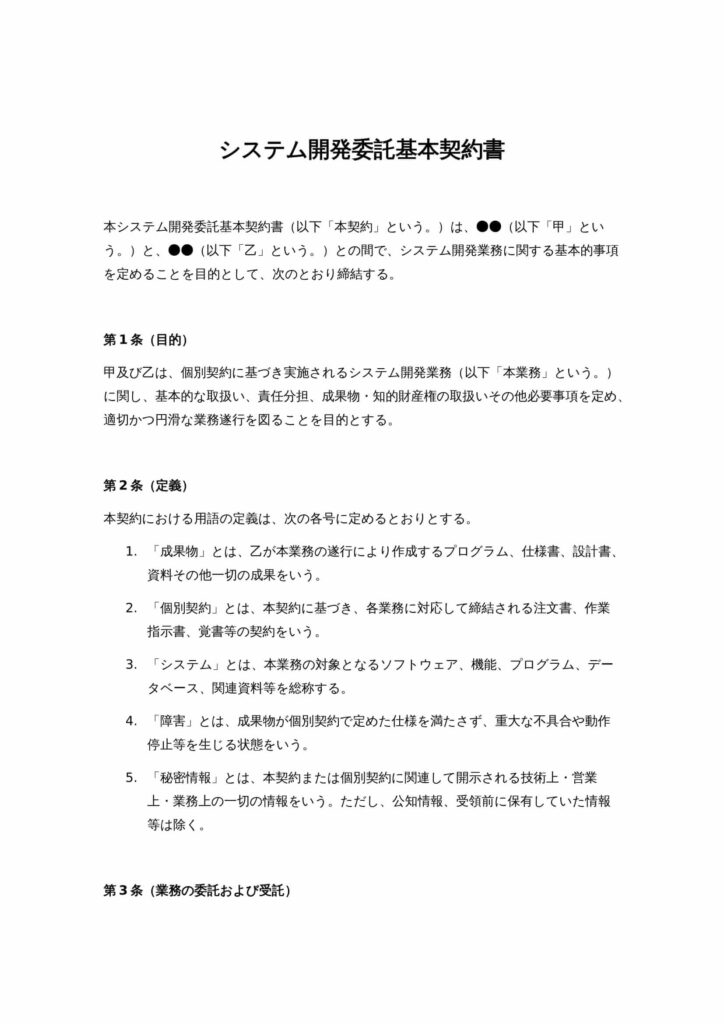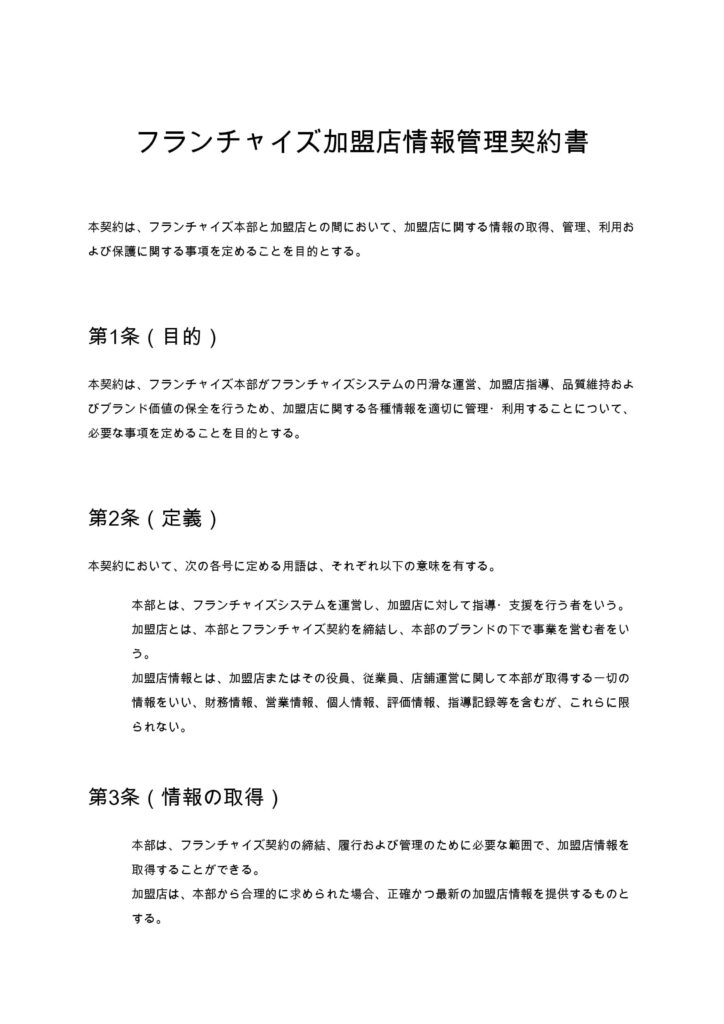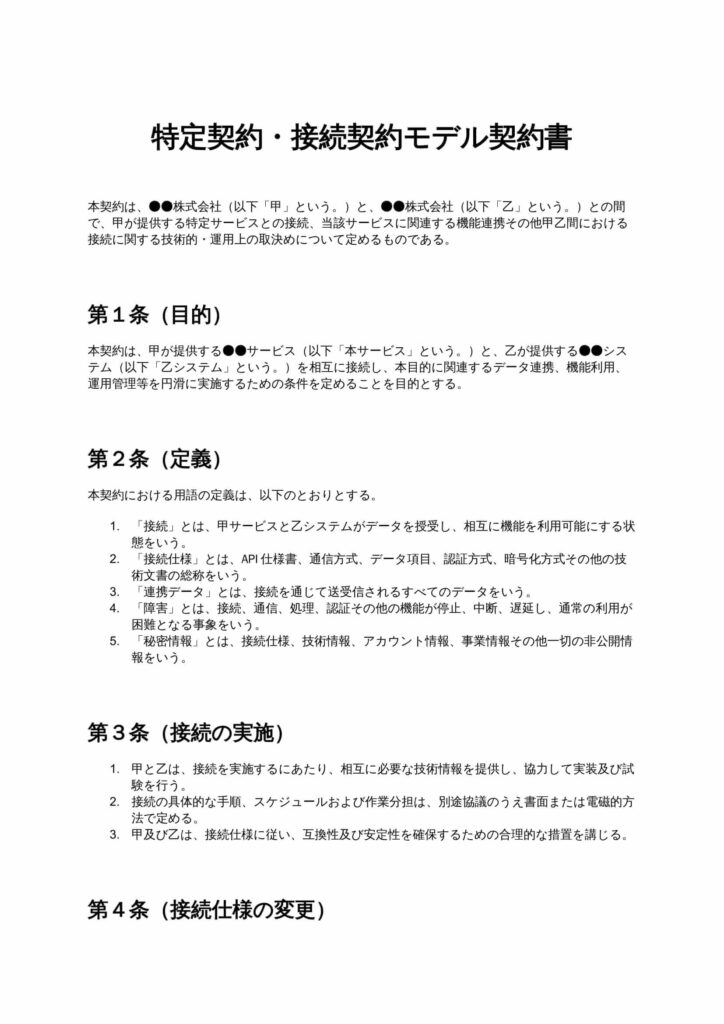秘密保持契約書(包括型NDA)とは?
秘密保持契約書(NDA:Non-Disclosure Agreement)は、当事者間で開示される秘密情報を保護するための契約書です。その中でも包括型NDAは、特定の案件やプロジェクトに限定せず、今後発生し得る様々な情報交換を包括的にカバーする契約形態です。
片務型NDAが「一方的に情報を開示し、相手方が守る」形式であるのに対し、包括型NDAは「双方が秘密情報を提供し合い、相互に守る」点に特徴があります。契約の有効期間中に発生する複数の取引や協議を網羅することができ、特に長期的な協力関係を前提とする企業間で選択されることが多い契約類型です。
包括型NDAが必要となるケース
- 包括型NDAは、次のような場面で必要とされます。
- 複数のプロジェクトにまたがって情報交換が行われる場合
- 技術提携や業務提携を前提とした長期的な関係がある場合
- 研究開発において双方がノウハウや技術情報を持ち寄る場合
- ベンチャー企業と大企業が協力して新規事業を検討する場合
- 委託契約やライセンス契約に至る前段階の協議で幅広い情報を共有する場合
こうした場面では、都度契約を結ぶのではなく包括的に守秘義務を設定しておくことで、実務負担を軽減し、情報漏えいリスクを防止することができます。
包括型NDAに盛り込むべき主な条項
包括型NDAを作成する際には、以下のような条項を盛り込むことが不可欠です。
- 目的条項:何のために秘密情報を交換するのかを明確化
- 定義条項:秘密情報の範囲、除外情報を具体的に規定
- 秘密保持義務:利用目的の限定、第三者への開示制限を規定
- 知的財産権:成果物や発明の帰属を定める
- 秘密情報の返還・廃棄:契約終了時の処理方法を規定
- 損害賠償・差止め:違反時の救済措置を規定
- 契約期間・存続条項:契約終了後の秘密保持期間を明記
- 準拠法・管轄:紛争発生時の準拠法と裁判所を規定
これらをバランスよく組み込むことで、包括的な情報交換に耐え得る契約内容となります。
条項ごとの解説と注意点
秘密保持条項
秘密保持条項は包括型NDAの中心部分です。受領者は開示者の事前承諾なしに秘密情報を第三者へ開示してはならず、また契約目的以外に利用してはなりません。さらに、従業員や関係会社に開示する場合も、必要最小限の範囲に限り、同等の義務を課す必要があります。注意点として、法令や裁判所命令による開示義務が生じた場合の手続きを明記しておくことが重要です。
契約期間・解除条項
包括型NDAは複数年にわたって効力を持たせることが一般的です。通常は2~5年程度とされますが、協力関係の性質に応じて設定する必要があります。また、契約終了後も秘密保持義務を一定期間存続させる規定を設けるのが通例です。解除については、相手方の重大な違反や合意解除を条件とすることが望まれます。
損害賠償条項
秘密保持義務に違反した場合には、開示者が被った損害を受領者が賠償する旨を定めます。ここでは、弁護士費用や逸失利益も含めるかどうかを明示することが実務上有効です。さらに、金銭賠償だけでなく差止め請求も可能とする条項を盛り込むことで、情報漏えいを未然に防止できます。
準拠法・裁判管轄
企業間取引の多くは日本法準拠とし、裁判管轄は東京地方裁判所または大阪地方裁判所が選ばれるケースが多いです。紛争発生時の手続きをあらかじめ明確にしておくことで、無用な対立を避けることができます。
契約書を作成・利用する際の注意点
包括型NDAを実務で利用する際には、以下の点に注意が必要です。
- 包括型であっても、対象外とする情報(除外情報)を丁寧に定義する
- 双務契約であるため、自社も秘密保持義務を負うことを認識する
- 子会社や外注先に再開示する場合の手続きを明記する
- 情報管理体制(アクセス制限・保存方法)を社内規程と合わせて整備する
- 有効期間終了後も一定期間は秘密保持義務が残る点に注意する
これらを怠ると、想定外のリスクを抱えたり、情報流出時に責任を問われる可能性があります。
注意点
- 包括型NDAは便利である反面、対象範囲が広すぎると不明確な部分が生じやすい
- 個別案件に関しては別途「プロジェクト限定型NDA」を結ぶ方が適切な場合もある
- 実務では契約書のひな形をそのまま使うのではなく、自社の事業内容に即して修正する必要がある
- 海外企業との契約では準拠法や管轄裁判所に特別の配慮が必要 – NDAだけでなく、将来の業務委託契約やライセンス契約と整合性を取ることが重要