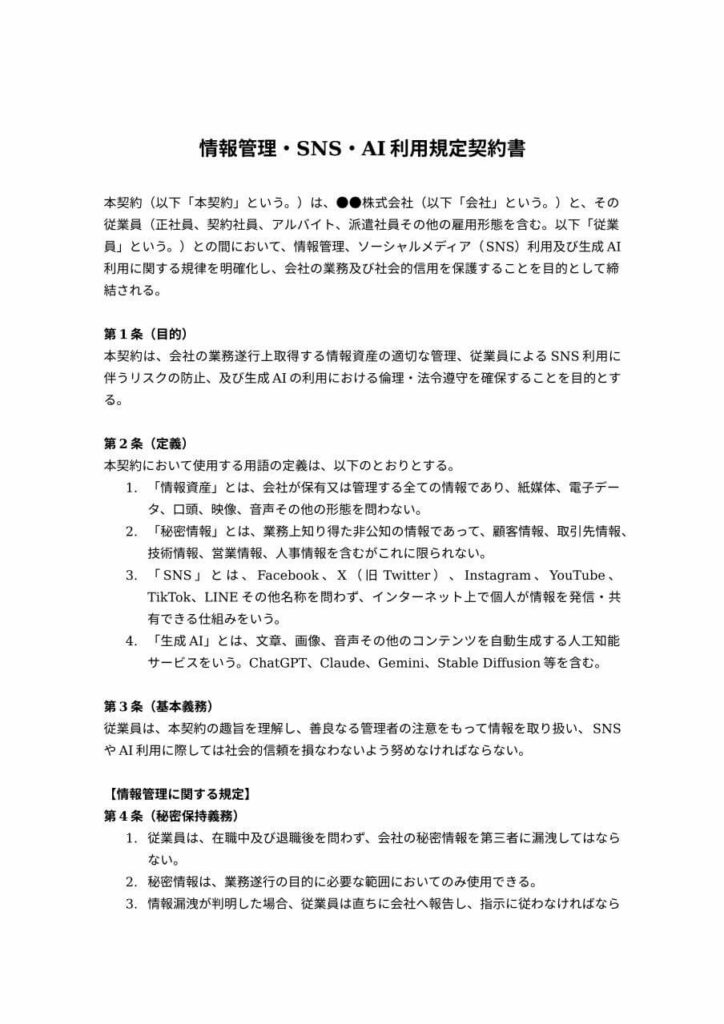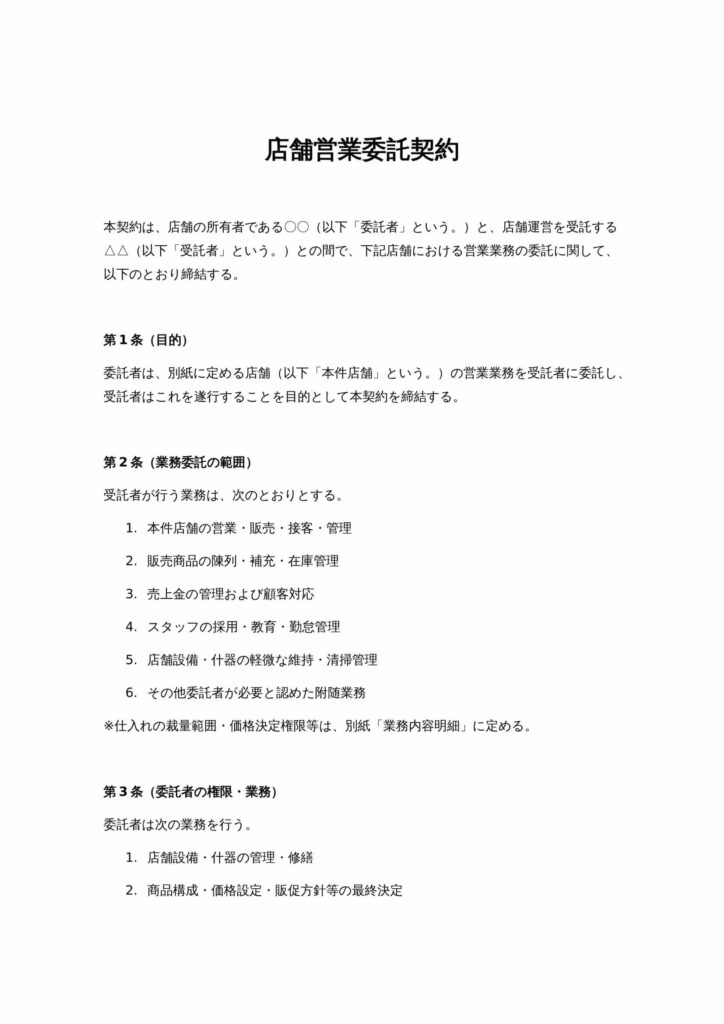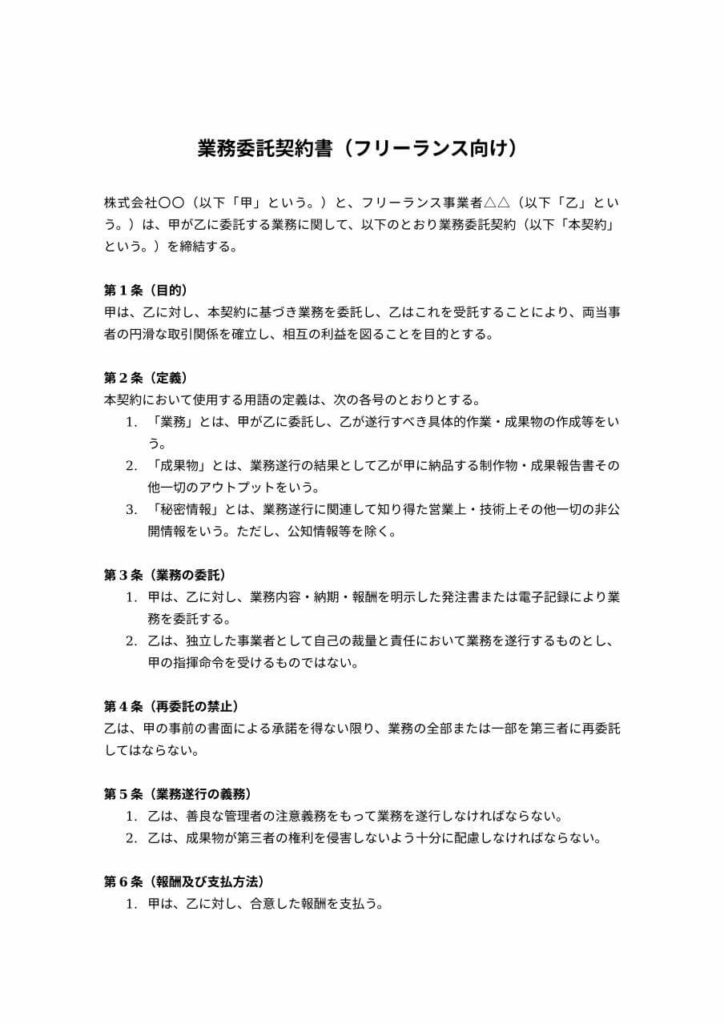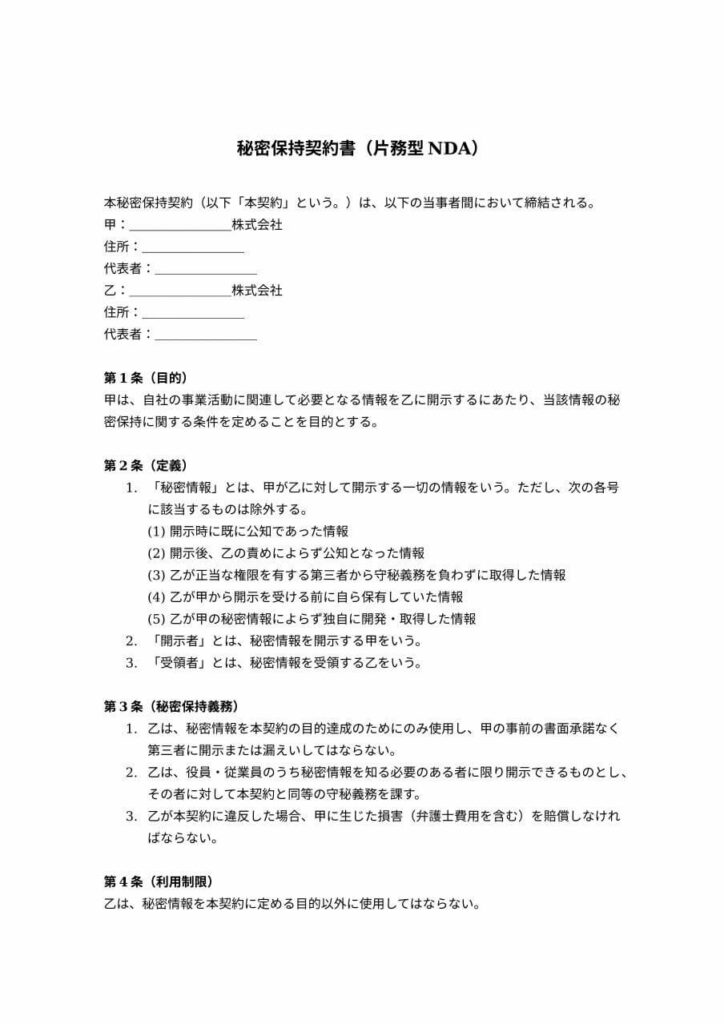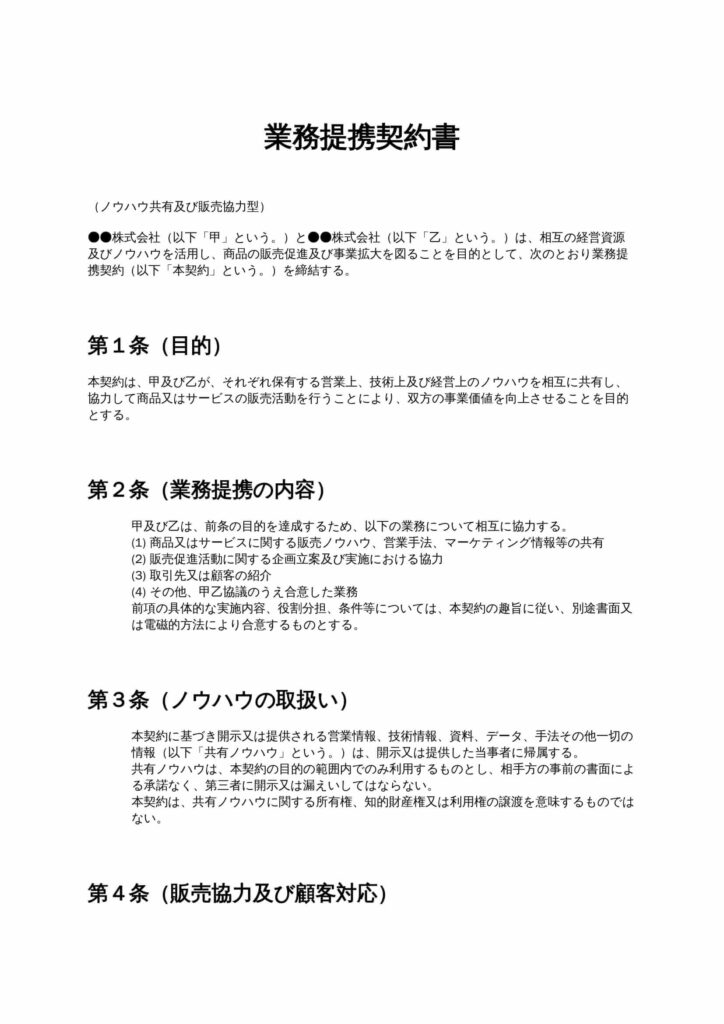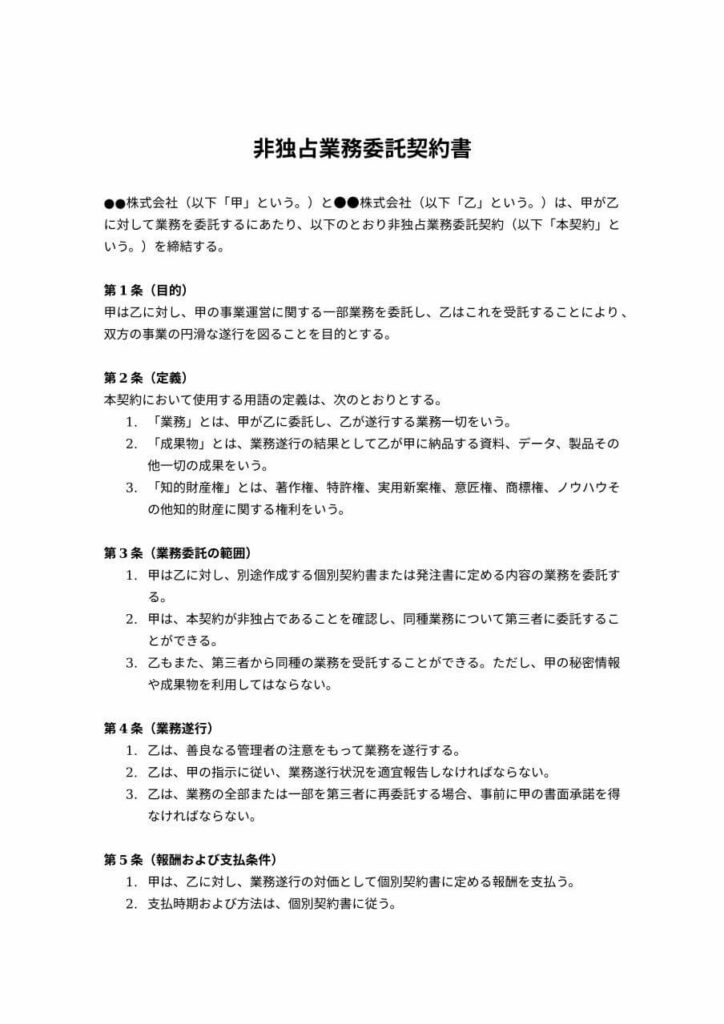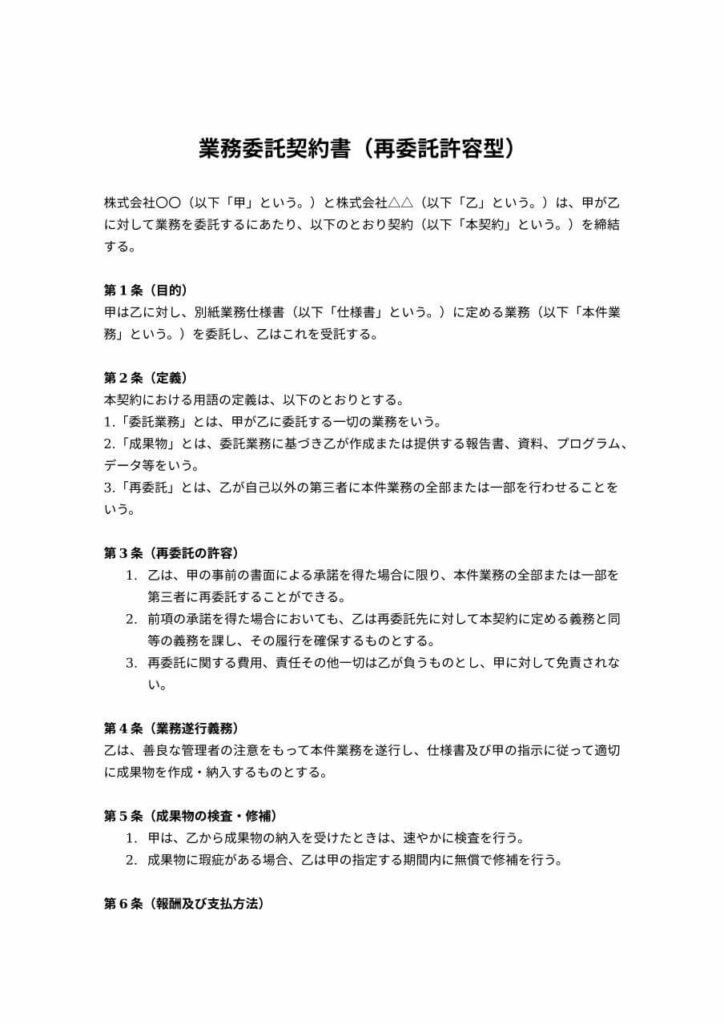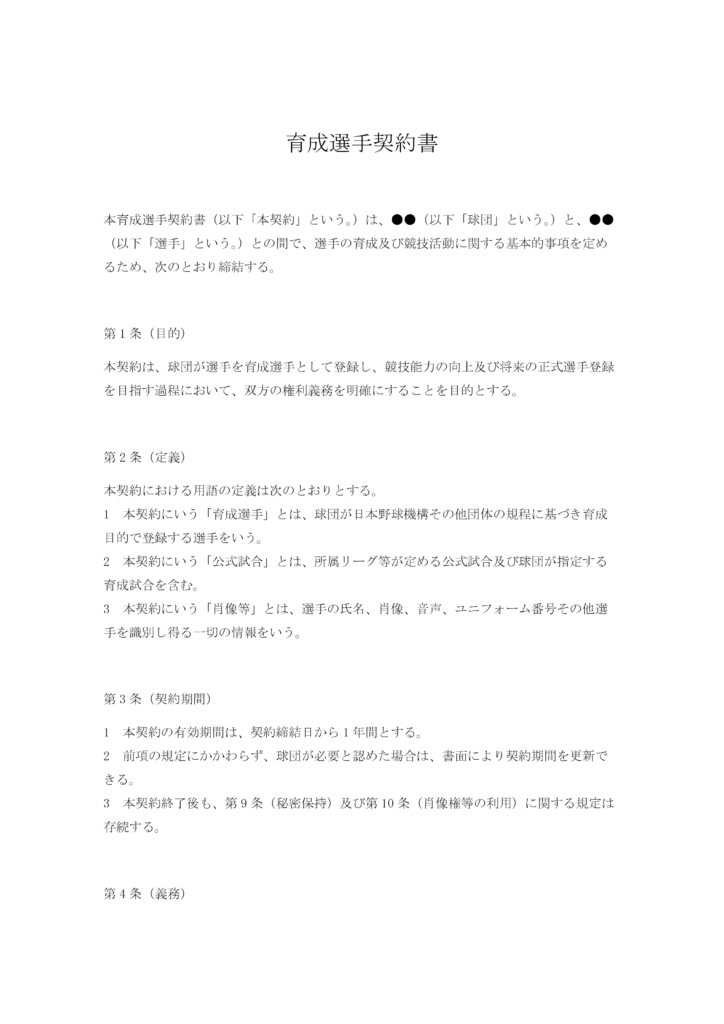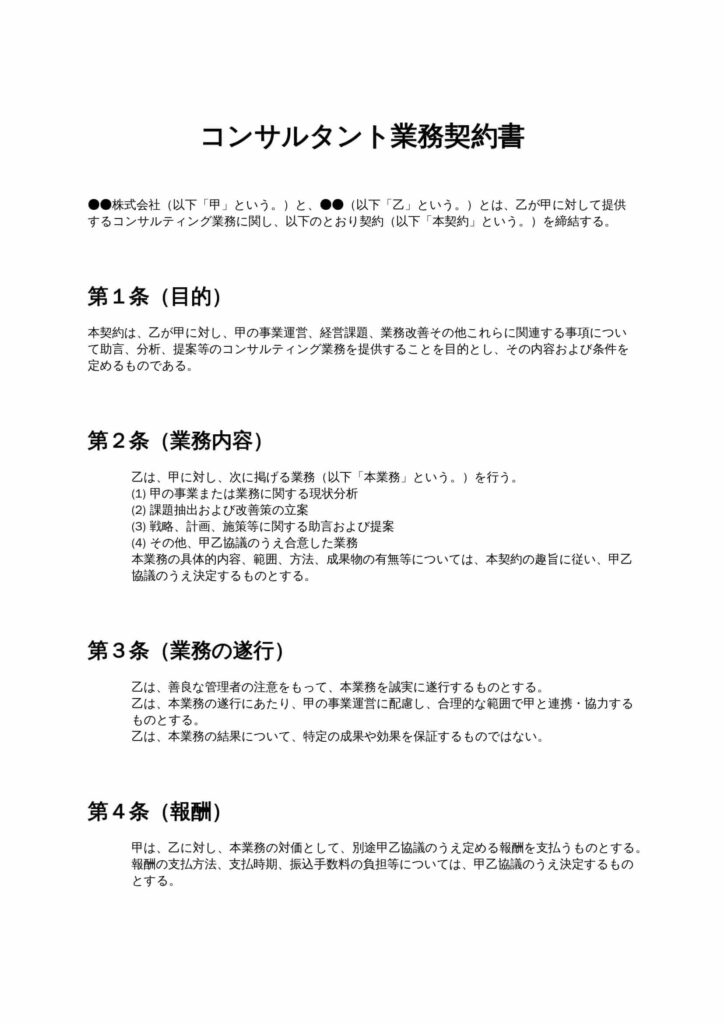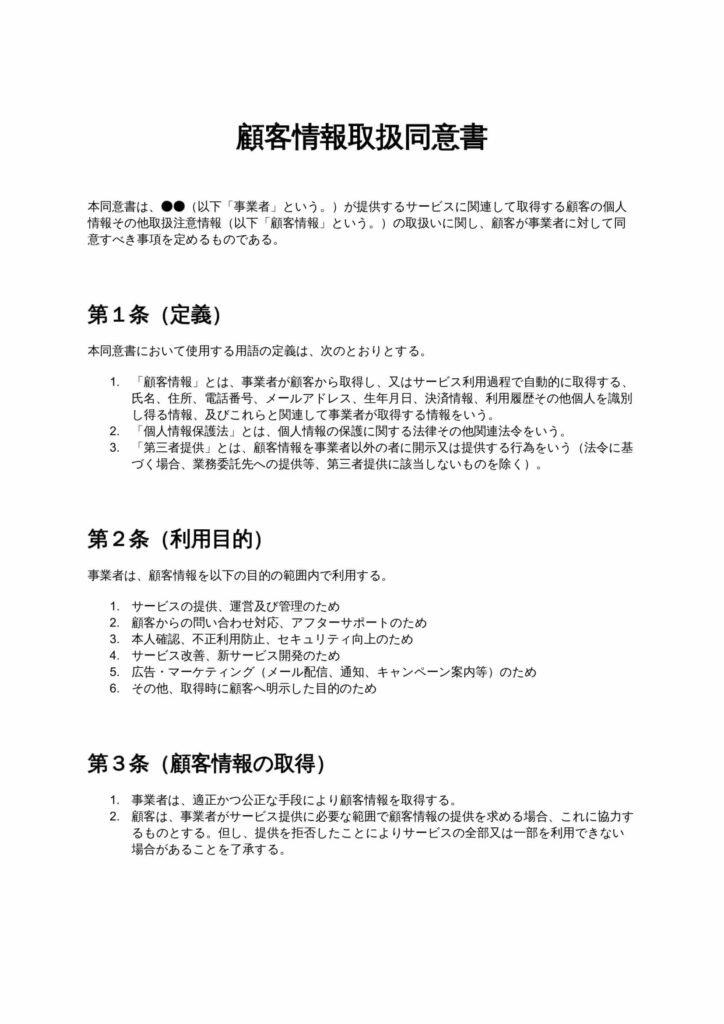情報管理・SNS・AI利用規定契約書とは?
情報管理・SNS・AI利用規定契約書とは、従業員が会社で働く中で取得する情報や、私的に利用するSNS、業務効率化のための生成AIについて、その利用方法と制約を明確化した契約書です。従来は秘密保持契約や就業規則に断片的に含まれていた内容を、近年の環境変化に合わせて包括的に整理したものといえます。
この契約書の目的は、以下の3点に整理されます。
- 会社の情報資産を適切に保護し、外部への漏洩を防止する
- 従業員によるSNS利用の自由と企業ブランド保護のバランスを取る
- 生成AI利用時に発生し得る法的・倫理的リスクを防ぐ
情報管理・SNS・AI利用規定契約書が必要となるケース
この契約書が必要となる典型的なケースは次のとおりです。
- 新規に従業員を雇用する際に、情報管理やSNS・AI利用ルールを契約で明示したい場合
- IT企業やスタートアップなど、顧客情報や開発中の技術が流出すれば大きな損害が発生する業種
- SNSによる発信活動が活発な社員が多い企業や、公式アカウントを運営している企業
- 社内で生成AIを業務に導入する企業(文章作成、設計支援、画像生成など)
- 退職後における情報漏洩リスクを明確に制御したい場合
こうした状況では、就業規則だけでは不十分であり、契約として従業員と合意を形成することがトラブル防止につながります。
契約書に盛り込むべき主な条項
この契約書に盛り込むべき必須の条項は以下のとおりです。
- 秘密保持義務
- 情報資産の利用制限と返還
- SNS利用の制限(業務上・私的利用)
- SNS炎上リスクへの対応義務
- 生成AIの利用範囲と入力制限
- AI成果物の確認責任
- 教育・研修の受講義務
- 違反時の懲戒処分と損害賠償責任
- 存続条項(退職後も秘密保持義務を存続させる)
- 紛争解決条項(準拠法・裁判管轄)
条項ごとの解説と注意点
秘密保持条項
従業員が業務を通じて知り得た顧客情報、取引先情報、技術情報はすべて秘密情報として扱うことを定めます。退職後も義務が存続する点が重要です。特にAI利用が普及する中で、外部サービスに機密情報を入力する行為も秘密保持違反にあたることを明記しておくと効果的です。
情報資産の管理条項
会社が貸与するPCやスマートフォン、クラウドアカウントの利用ルールを明示します。USBメモリでの情報持ち出しを禁止する、退職時にはすべて返還・削除するなど、実務でよく問題となる場面を具体的にカバーします。
SNS利用条項
業務中の私的SNS利用禁止、業務外であっても会社や顧客を誹謗中傷することの禁止を規定します。さらに、会社名や所属をSNSで公開する場合のルールを細かく記すことが望まれます。SNS炎上リスクは企業の信用失墜につながるため、発生時の報告義務と対応協力を明記することが不可欠です。
生成AI利用条項
生成AIの利用を承認制とし、入力情報を制限することが中心です。特に顧客データや設計情報をAIに入力すると、その情報が外部に蓄積されるリスクがあるため、明確に禁止する必要があります。また、成果物をそのまま外部に提出せず、著作権や正確性を人的に確認する義務を課すことでリスクを軽減できます。
教育・研修条項
従業員に対し、情報管理・SNS・AI利用に関する定期的な研修を受講させる条項を設けます。ルールを定めるだけでなく、理解を浸透させることがトラブル防止の実効性を高めます。
損害賠償・懲戒条項
従業員が規定に違反した場合、会社は損害賠償を請求できることを明示します。さらに就業規則と連動して懲戒処分の対象とすることで、抑止力を強められます。
契約書を作成・利用する際の注意点
- 契約書を作成・運用する際の実務的な注意点は以下のとおりです。
- 社内規程(就業規則や情報セキュリティポリシー)と矛盾がないか確認する
- 実際の業務フローに即した具体性を持たせる(例えば「USB持ち出し禁止」など)
- AI利用に関しては利用範囲を広くしすぎず、承認制やチェック体制を組み込む
- SNS利用制限は過度に従業員の表現の自由を制約しないようバランスを取る
- 違反が発覚した場合の社内フロー(報告窓口、対応責任者)を定めておく
- 必要に応じて専門家(弁護士・社労士)に確認して、法的リスクを点検する
注意点
- この契約書は、従業員との信頼関係を損なわないよう「一方的に制約する規程」ではなく「情報と会社を守るための合意」であることを明示することが望ましい。
- SNSやAIの技術進歩は速いため、契約書は数年ごとに見直す必要がある。
- 実務に落とし込む際は、就業規則、社内ガイドライン、教育制度とセットで運用することで効果を最大化できる。