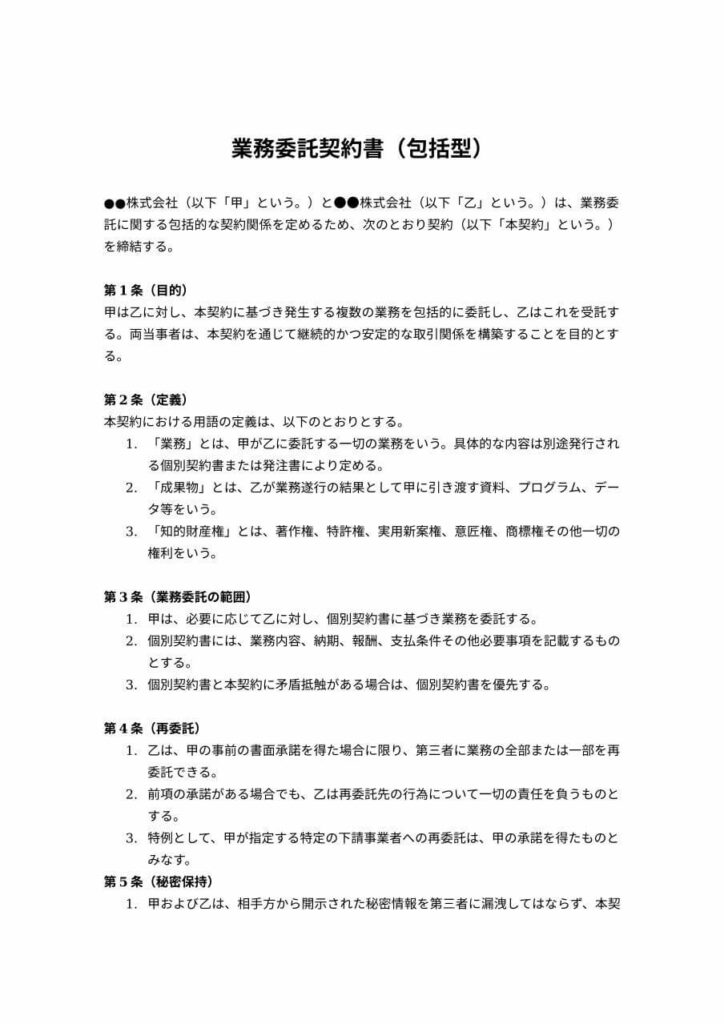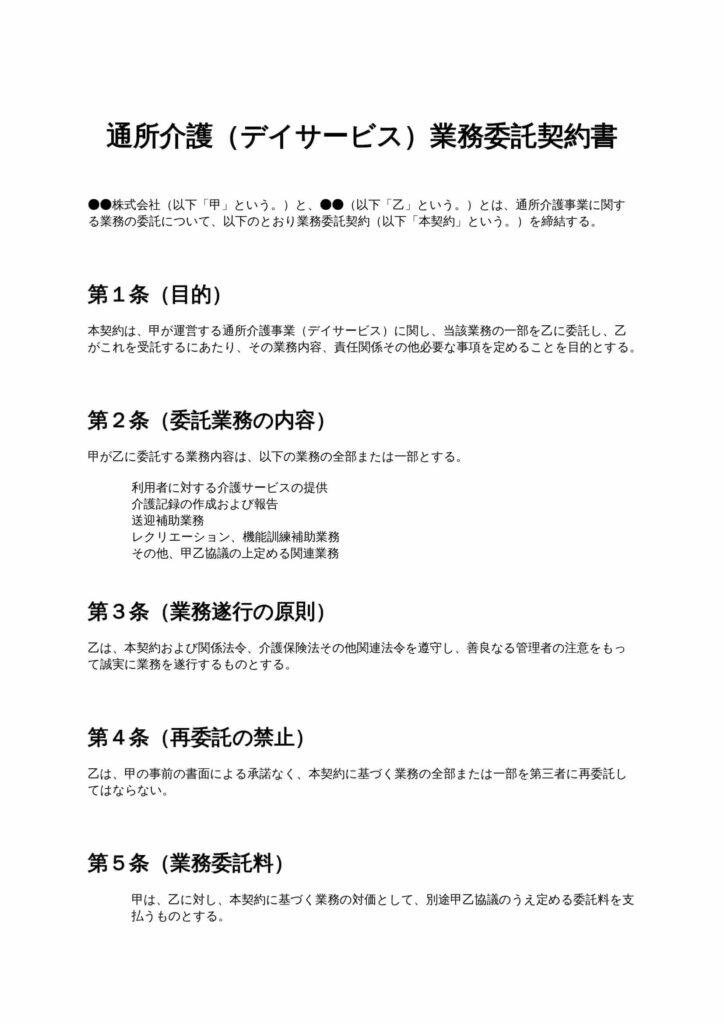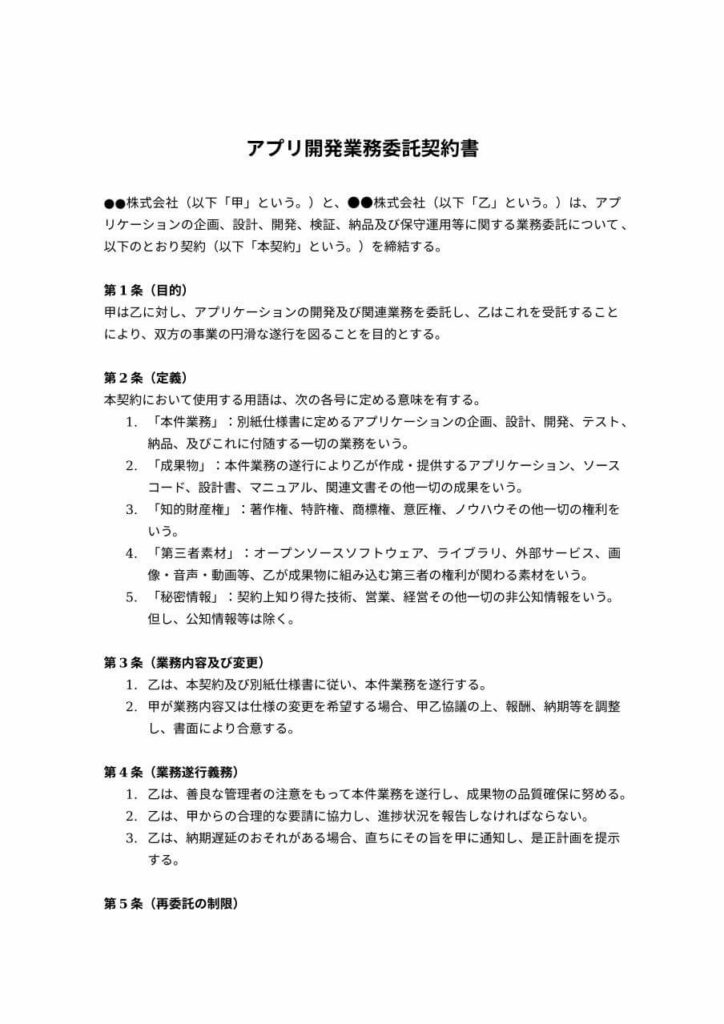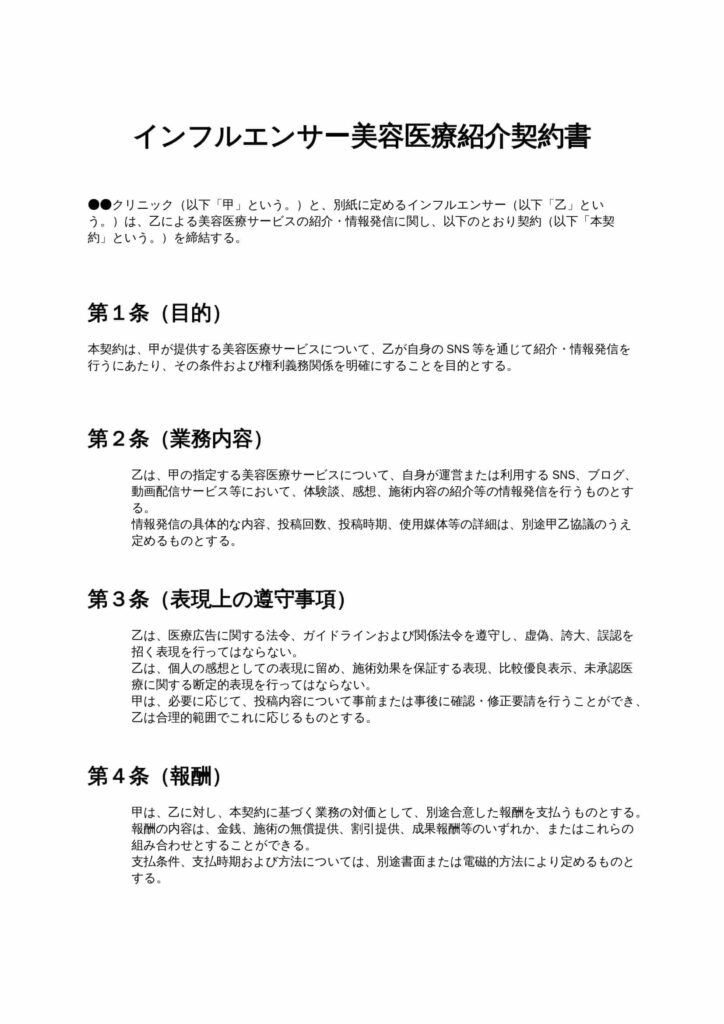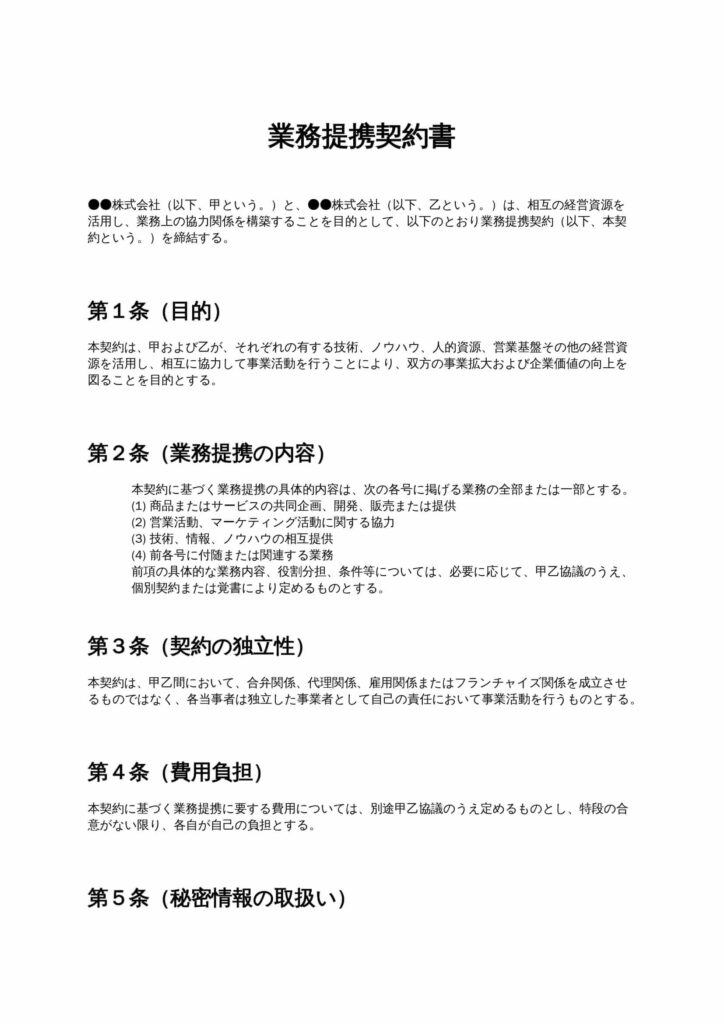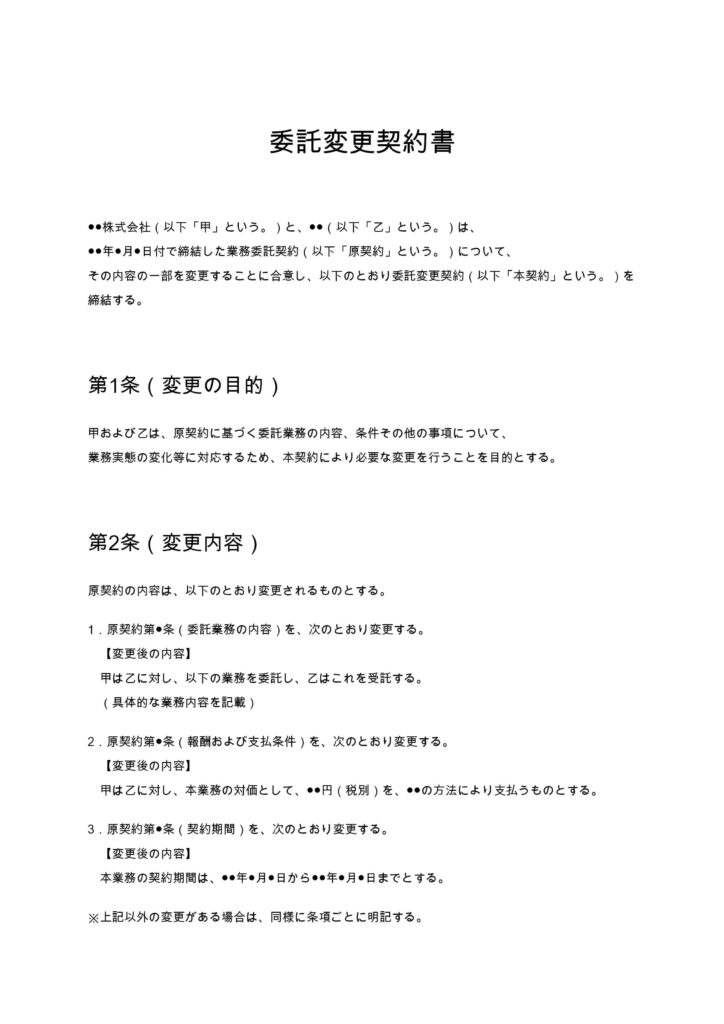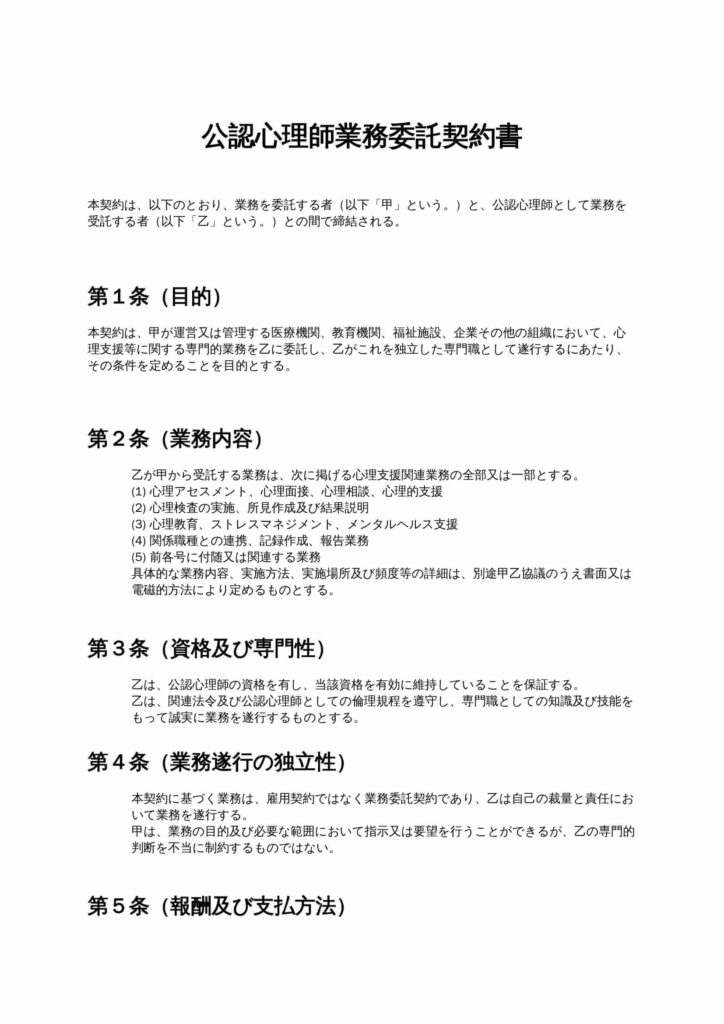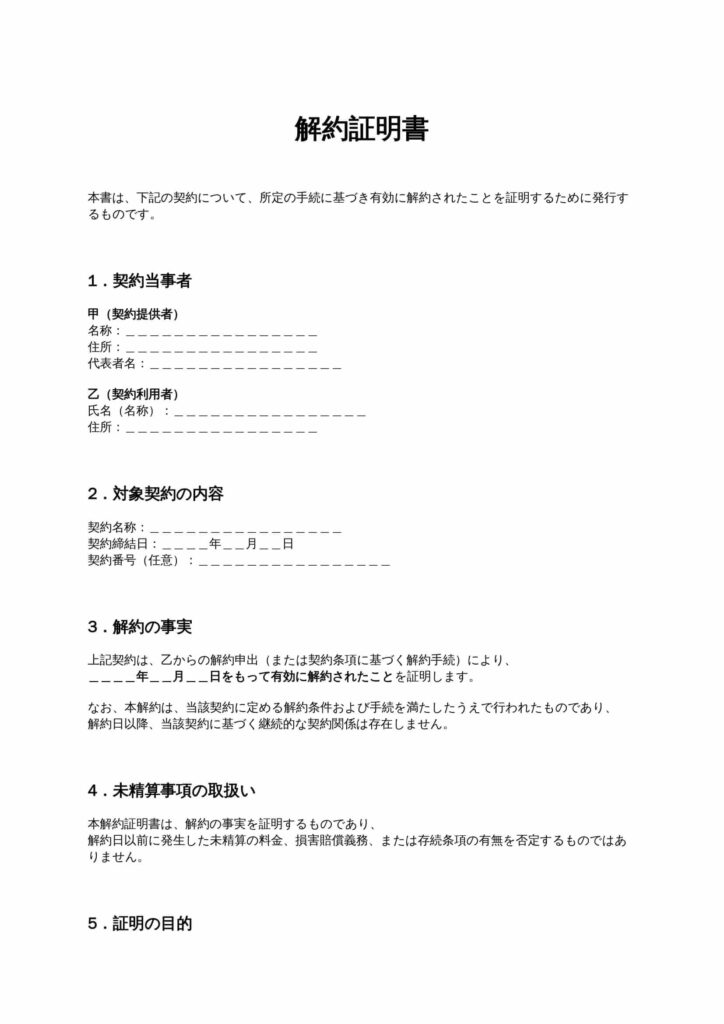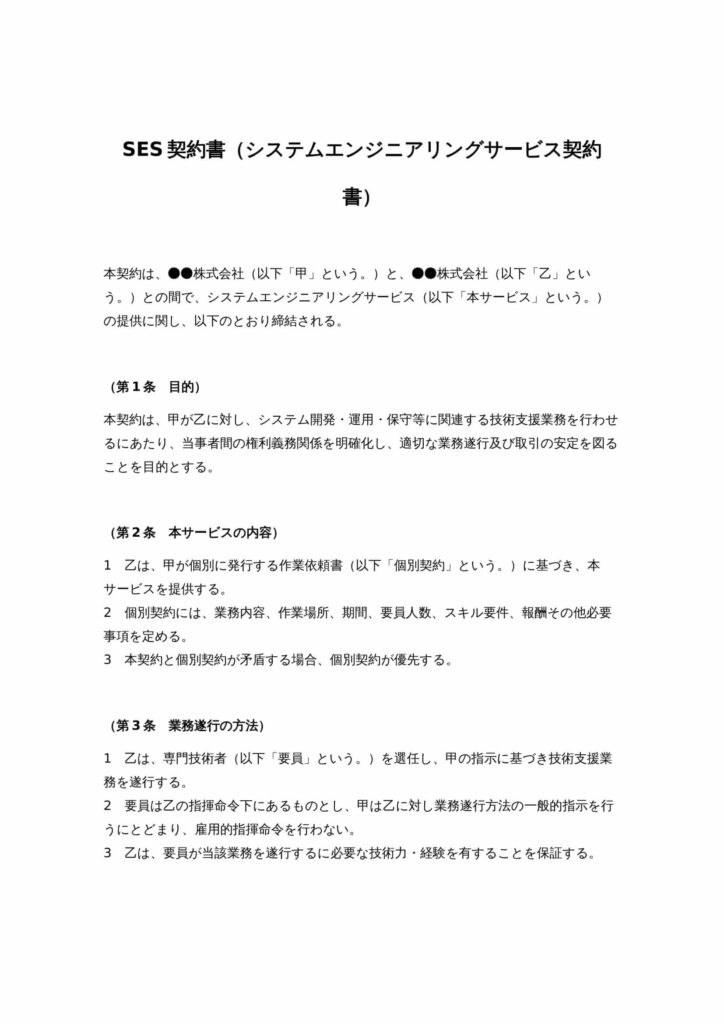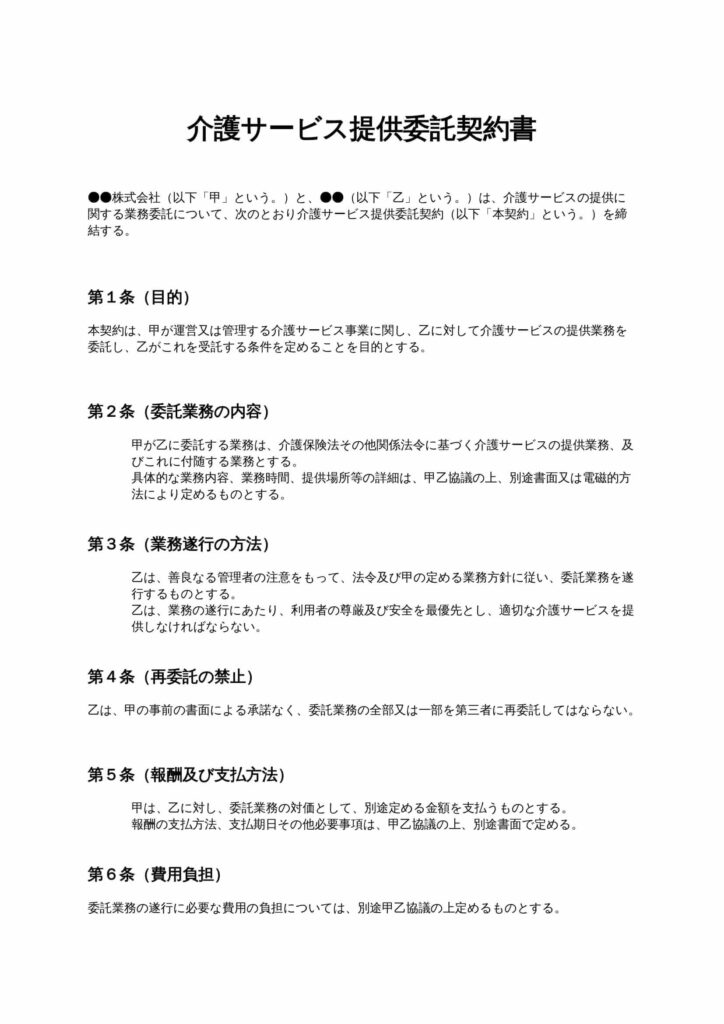業務委託契約書(包括型)とは?
業務委託契約書(包括型)とは、複数の業務を包括的に対象とし、長期的な取引を前提として取り交わされる契約書です。通常の業務委託契約書(基本型)が個別の案件を対象とするのに対し、包括型は契約期間中に発生する多様な業務を一括してカバーできる点が特徴です。企業間のパートナーシップを強化し、柔軟かつ効率的に業務を進めるために利用されます。
業務委託契約書(包括型)が必要となるケース
- システム開発、保守、運用を長期にわたり同一事業者へ委託する場合
- 広告代理店やコンサルティング会社と複数分野で取引を行う場合
- 人材派遣やアウトソーシング企業に幅広い業務を依頼する場合
- 複数プロジェクトが並行して発生する企業間取引を一括して契約で管理したい場合
業務委託契約書(包括型)に盛り込むべき主な条項
- 契約の目的と範囲
- 委託業務の内容と個別契約書との関係
- 再委託の可否と条件
- 報酬および支払条件
- 知的財産権の帰属
- 秘密保持義務
- 契約期間と更新・解除の条件
- 損害賠償責任と遅延損害金
- 不可抗力条項
- 紛争解決方法と裁判管轄
条項ごとの解説と注意点
契約目的・範囲
包括型契約では、契約期間中に発生する業務を幅広く対象とするため、目的と範囲を明確に記載することが重要です。特に「個別契約書」との関係性を整理し、矛盾や不明確さを避けることで、紛争防止につながります。
再委託条項
業務の一部を第三者に再委託できるかどうかは実務上重要です。包括型契約では、多数の業務が想定されるため、原則禁止としつつ「甲の事前承諾がある場合のみ許可」とするのが一般的です。特例として、甲が指定する業者への再委託を認める条項を設けることも可能です。
報酬・支払条件
包括契約では報酬体系が複雑化しやすいため、原則的な支払条件を本契約に記載し、具体的な金額や支払スケジュールは個別契約書に委ねる形が適しています。遅延損害金条項を加えることで、債務不履行時のリスクを抑えられます。
知的財産権の帰属
成果物が発生する業務を含む場合、知的財産権の帰属を定めることが不可欠です。原則は委託者に帰属させる一方で、受託者が保有する既存ノウハウについては留保できるようにしておくと、公平な関係を保てます。
秘密保持条項
包括型では複数業務にわたって取引するため、秘密保持義務の範囲を広く設定することが求められます。契約終了後も一定期間存続させる規定を設け、情報漏洩リスクを低減します。
契約期間・解除条項
包括型は長期契約となることが多いため、契約期間と更新の仕組みを明確にし、解除事由も具体的に定めておく必要があります。契約違反や支払不能など重大な事由が発生した場合には、催告なしで解除できる条項を置くことが一般的です。
損害賠償条項
債務不履行や成果物の瑕疵に備え、損害賠償条項を規定します。乙が納品した成果物に問題があれば修補請求や代替品納入を求める条項を入れておくと実務上安心です。
不可抗力条項
天災地変や法令改廃など不可抗力による履行不能時の責任免除条項を設けることで、予測不能なリスクに対応できます。
準拠法・裁判管轄
最終的な紛争処理の場を事前に定めておくことは必須です。企業間契約では「東京地方裁判所」など特定の裁判所を専属管轄とするのが一般的です。
契約書を作成・利用する際の注意点
- 包括型は柔軟性が高い一方で、条項が曖昧だとトラブルの原因になります。
- 個別契約書との整合性を常に意識し、矛盾が生じないよう管理することが大切です。
- 契約解除事由を広く設定しすぎると、受託者にとって不利になる場合があるため、バランスに配慮してください。
- 知的財産権や秘密保持の存続条項は必ず明記しておきましょう。
- 実際に利用する際は、事業規模や業務内容に応じてカスタマイズし、必ず専門家の確認を受けることを推奨します。