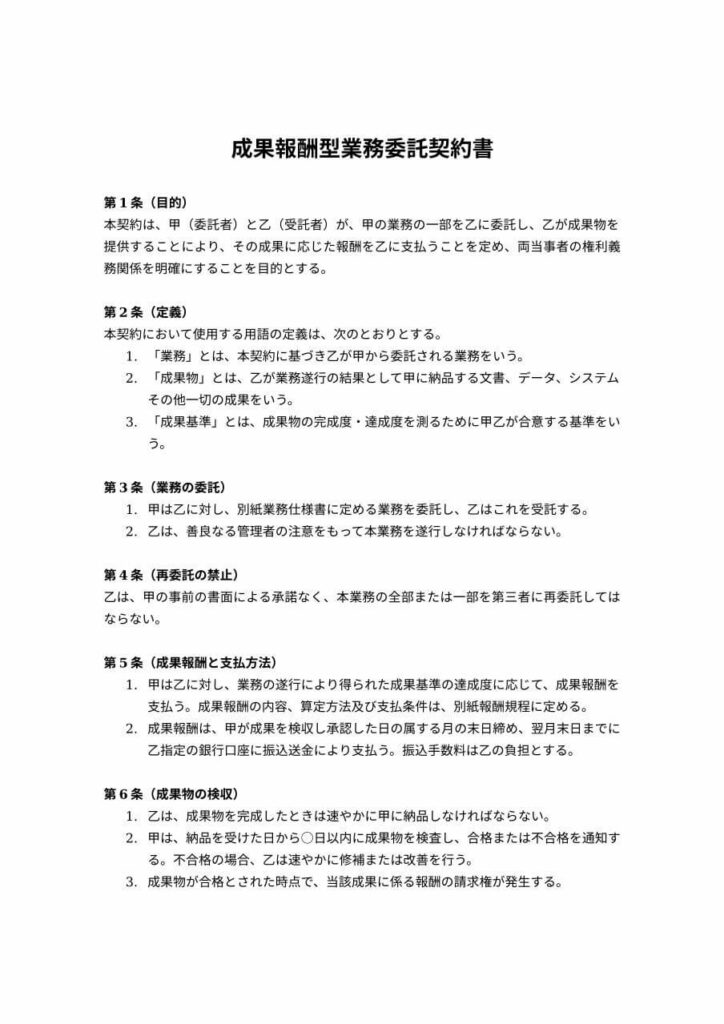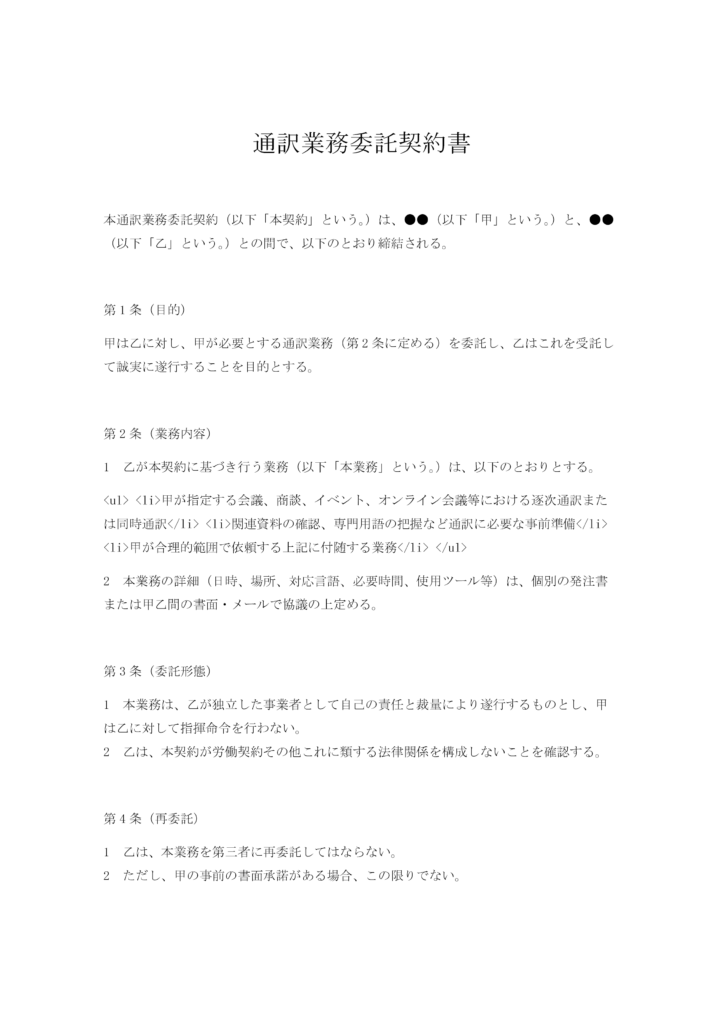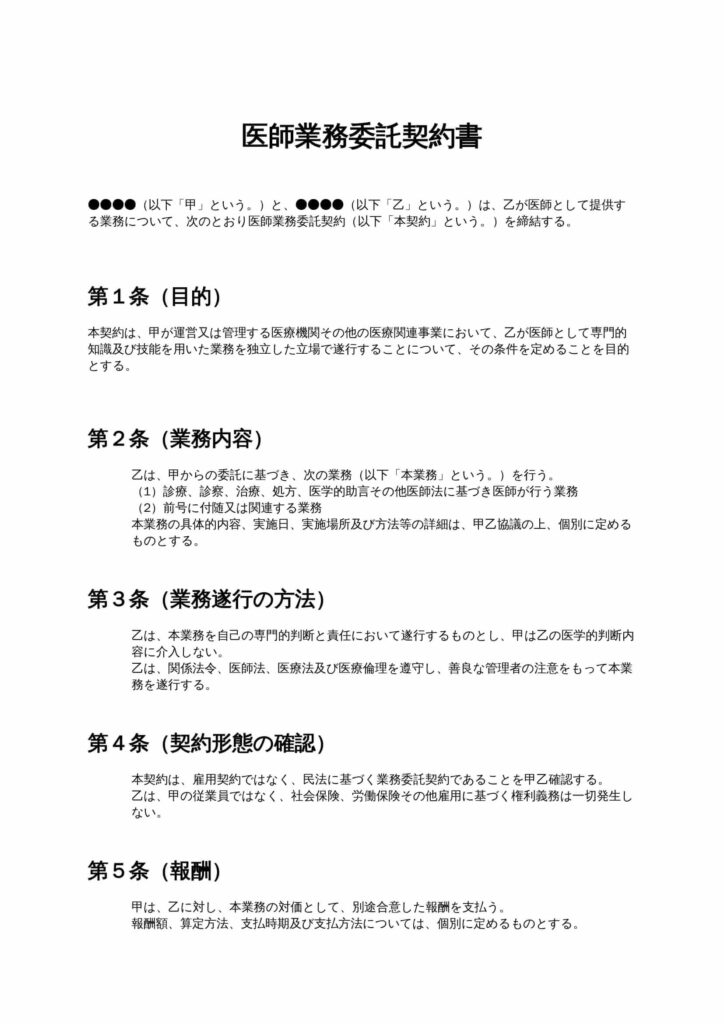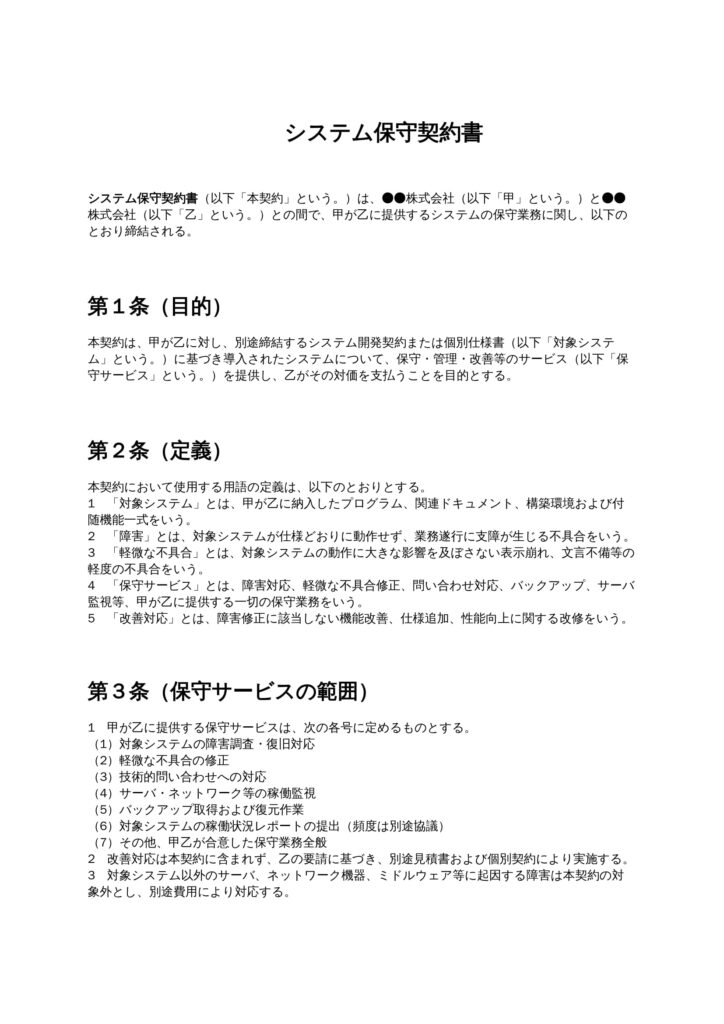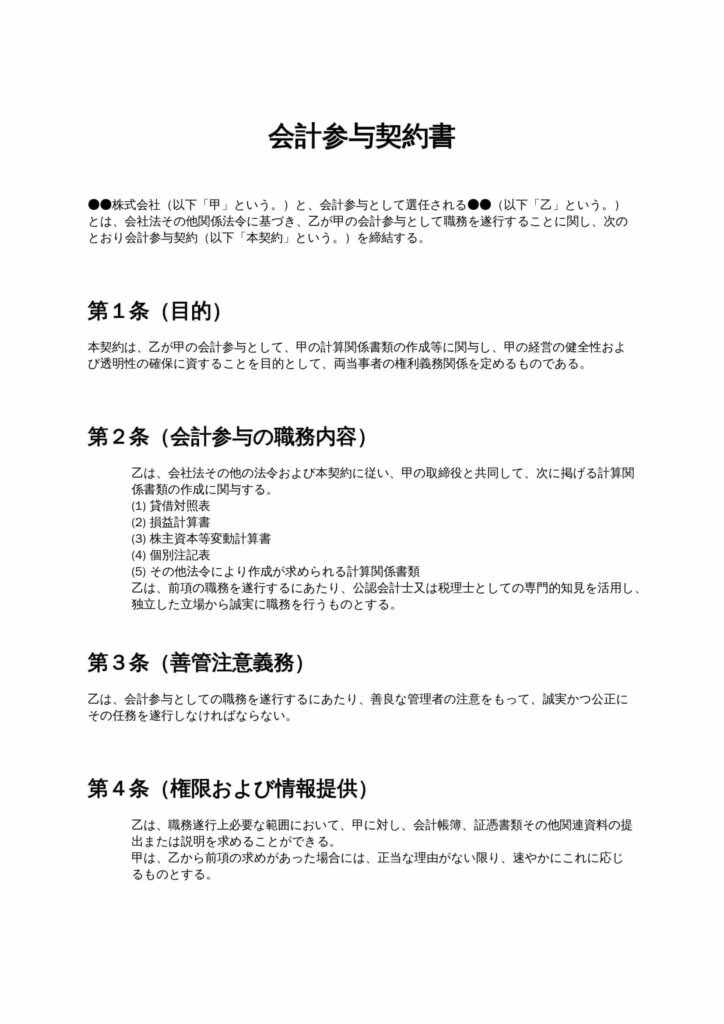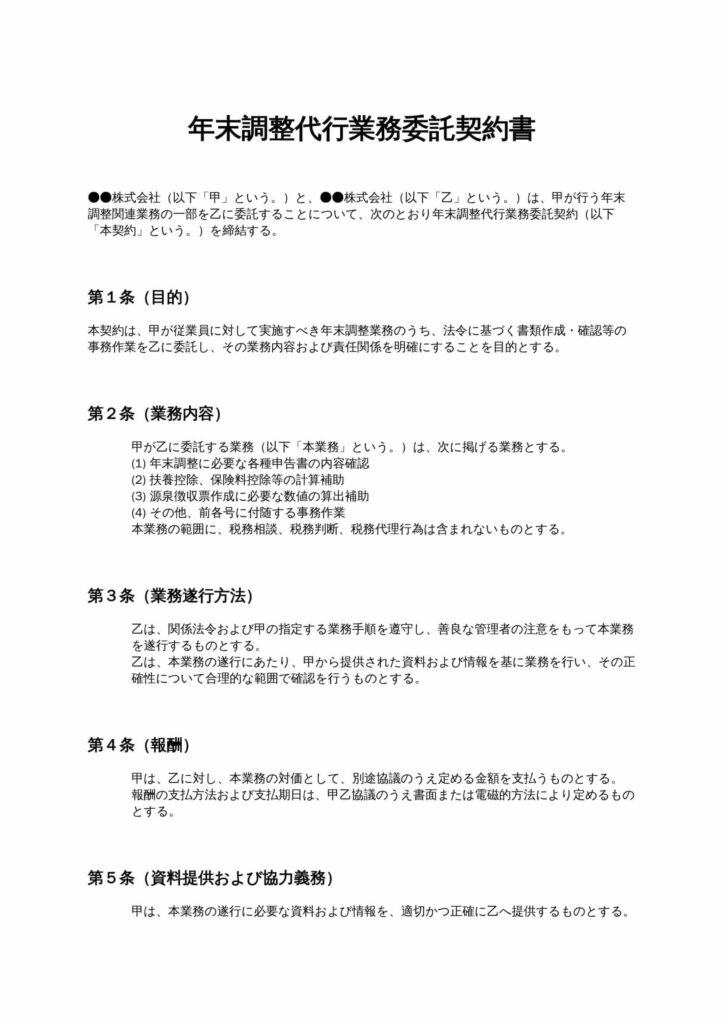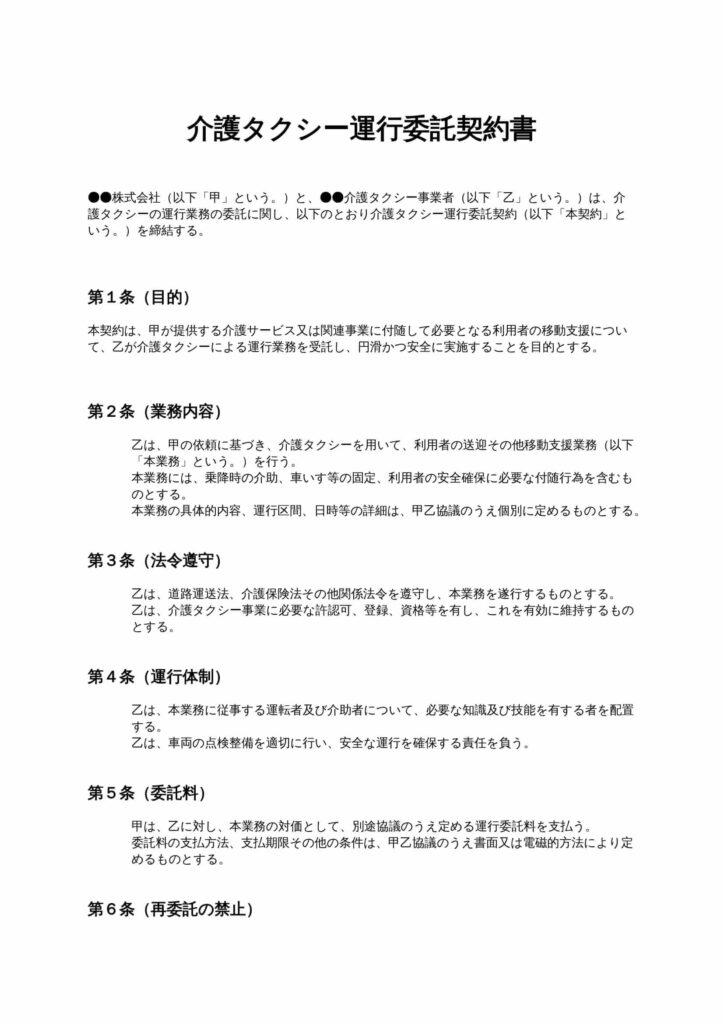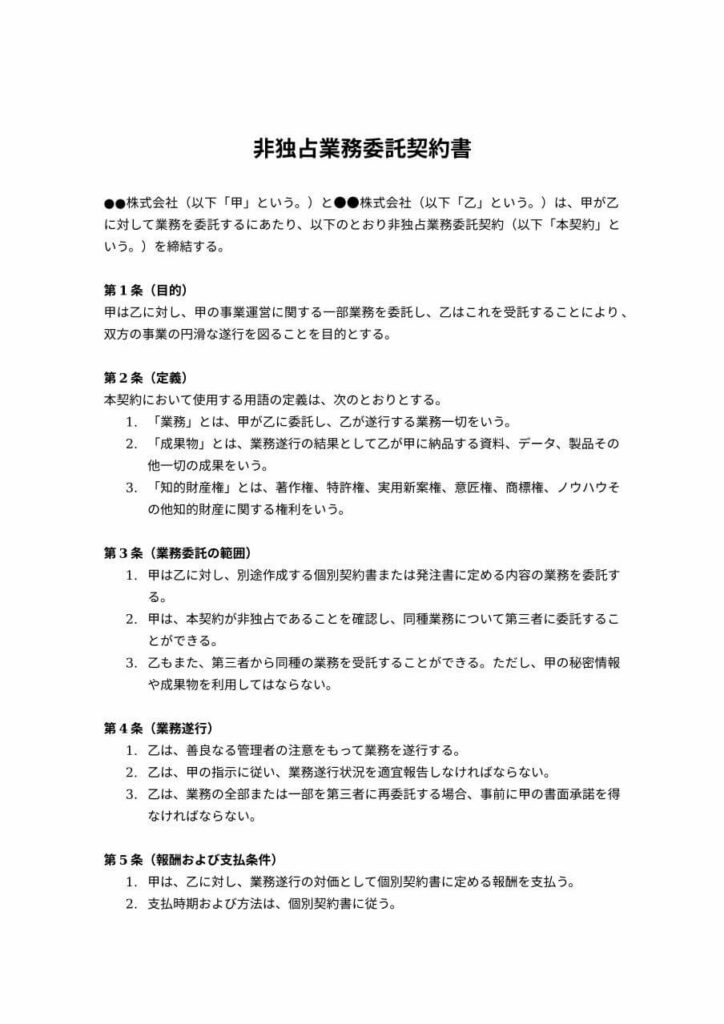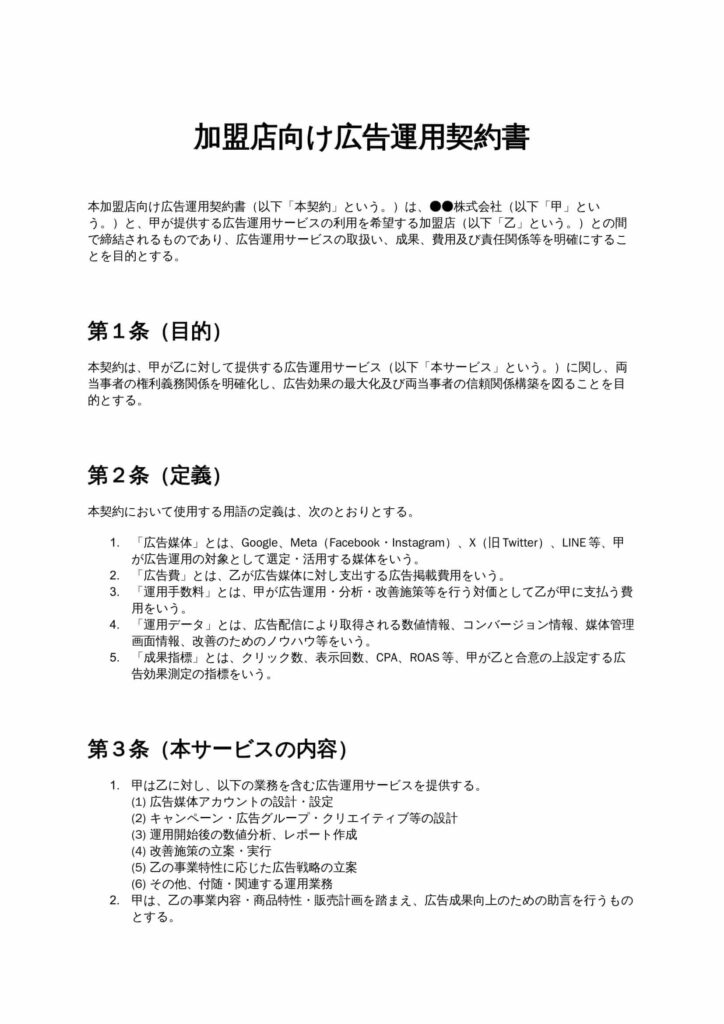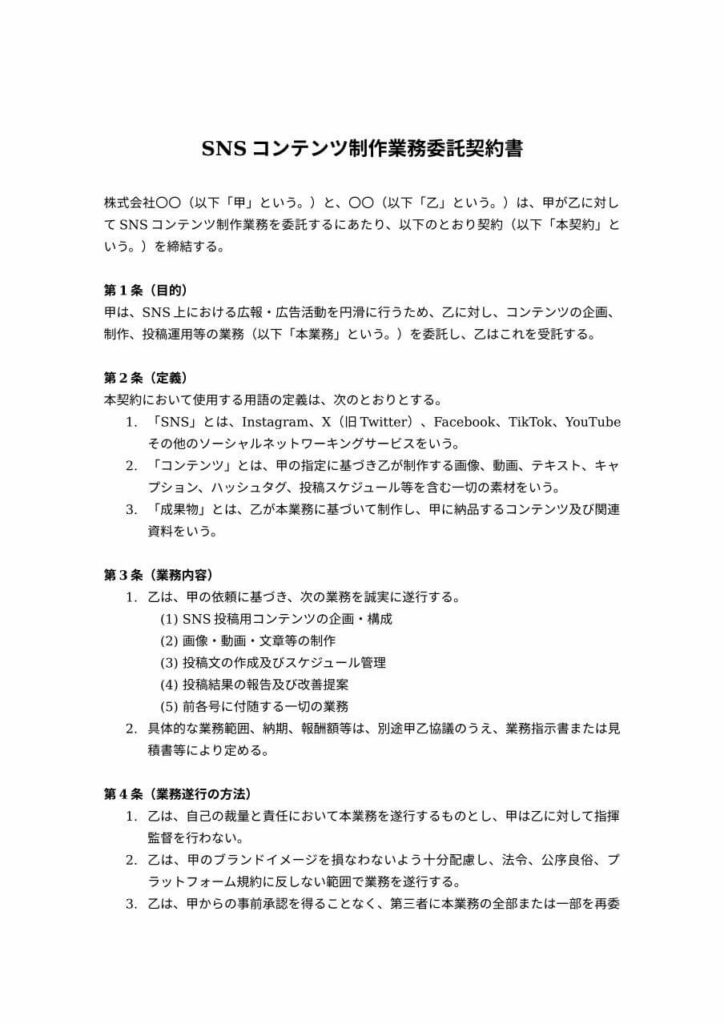成果報酬型業務委託契約書とは?
成果報酬型業務委託契約書とは、業務を遂行した時間や労力ではなく、実際に得られた成果を基準として報酬を支払う契約形態を定める文書です。一般的な業務委託契約では、作業時間や固定額での報酬設定が多いのに対し、本契約は成果達成が前提となるため、よりシビアな契約内容になります。
成果報酬型契約の特徴は次の点にあります。
- 成果が明確に定義され、数値化や客観的に測定できることが前提となる
- 甲(委託者)は、リスクを抑えつつ成果に応じた支出が可能
- 乙(受託者)は、成果次第で大きな報酬を得られる可能性がある反面、成果がなければ報酬を得られないリスクを負う
そのため、契約においては「成果の定義」を明確にすることが最も重要です。
成果報酬型業務委託契約書が必要となるケース
成果報酬型の契約は、特に次のようなケースで用いられます。
- 広告代理店やマーケティング会社が「売上の増加」「申込件数」などを基準に成果を測る場合
- 営業代行会社が「成約件数」や「新規顧客獲得数」に応じて報酬を得る場合
- ITエンジニアや開発会社が「システムの稼働率」や「機能リリース数」などを基準とする場合
- 採用コンサルタントや人材紹介会社が「採用決定人数」に応じて報酬を得る場合
いずれのケースも「成果物が明確に定義できる」ことが前提となります。
成果報酬型業務委託契約書に盛り込むべき主な条項
成果報酬型契約書では、通常の業務委託契約に加えて、成果に基づく報酬条件を明確に規定する必要があります。盛り込むべき条項には以下があります。
- 契約目的
- 定義(成果物・成果基準の明確化)
- 業務内容と範囲
- 成果報酬の額、算定方法、支払条件
- 成果物の検収方法
- 知的財産権の帰属
- 秘密保持義務
- 契約期間と自動更新
- 契約解除と損害賠償
- 管轄裁判所
条項ごとの解説と注意点
契約目的条項
成果報酬型契約では「業務の遂行そのもの」よりも「成果の達成」が重視されます。そのため、契約目的に「成果に基づき報酬を支払う契約であること」を明確に記載することで、後の解釈トラブルを防げます。
定義条項
最も重要なのが「成果物」「成果基準」の定義です。例えば「売上増加」や「成約件数」といった成果が曖昧なまま契約すると、成果の有無について紛争が起きやすくなります。契約書には具体的に「新規顧客契約数を○件以上」などの数値を盛り込むのが望ましいです。
成果報酬条項
成果報酬の額や計算方法は明確にする必要があります。例えば「新規契約1件につき○万円」「売上金額の○%」などと定めます。また、報酬が発生する時期(検収後、入金後など)を規定することも不可欠です。
成果物の検収条項
成果報酬が発生するには、甲による検収・承認が前提です。検収期間を明確にし、乙が修正対応する条件も明記することで、紛争を予防できます。
知的財産権条項
納品物の著作権やノウハウの帰属を明確にします。通常、納品物の権利は甲に帰属させ、乙の既存ノウハウは乙に留保する形が一般的です。
秘密保持条項
受託者は業務遂行により甲の営業秘密や顧客情報を知り得るため、秘密保持条項を入れることは必須です。
契約期間・解除条項
契約の有効期間と、自動更新の有無を定めます。また、成果が一定期間出ない場合に甲が契約解除できる条件も記載しておくと実務上安心です。
損害賠償条項
成果報酬型はトラブルに発展しやすいため、契約違反があった場合の損害賠償責任を定める必要があります。
準拠法・裁判管轄条項
紛争解決のため、準拠法を日本法とし、管轄裁判所を特定しておくことが望まれます。
契約書を作成・利用する際の注意点
成果報酬型契約は双方にとってメリットが大きい反面、リスクも存在します。作成時には以下の点に注意することが重要です。
- 成果の定義を曖昧にせず、数値や具体的事実で規定する
- 報酬の支払条件を「売上発生時」「入金確認時」など明確にする
- 検収期間や修正義務を明記し、検収トラブルを防ぐ
- 成果が出なかった場合の取り扱い(報酬ゼロ、最低保証報酬など)を定める
- 解約条件を定め、双方が不利益を被らないよう調整する
こうした注意点を押さえることで、契約の透明性を高め、実務におけるリスクを軽減できます。