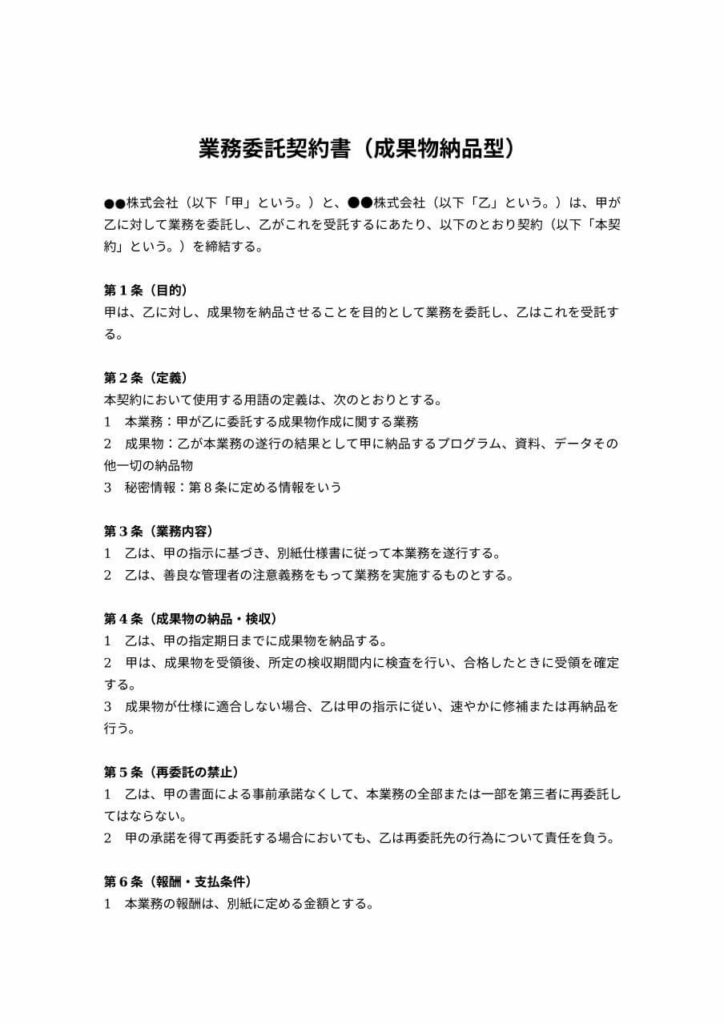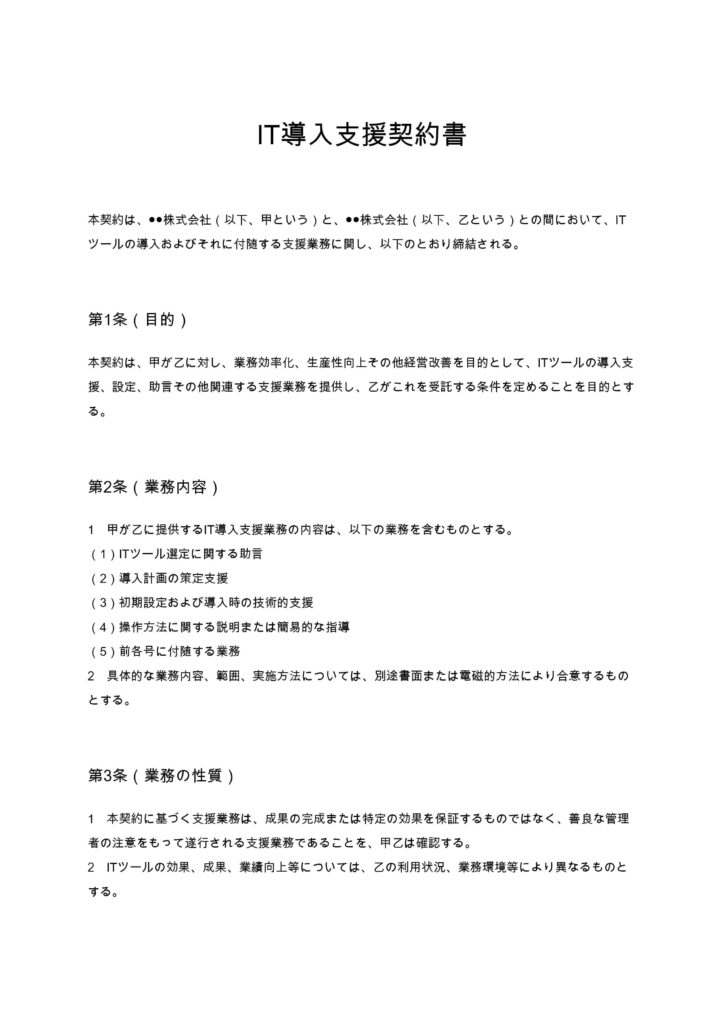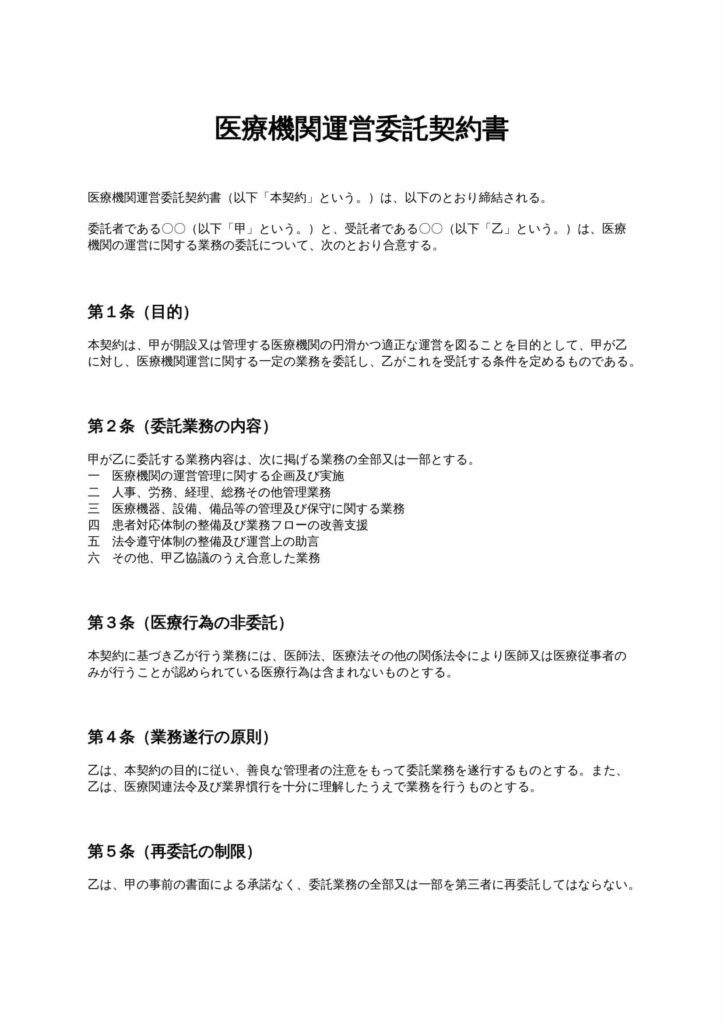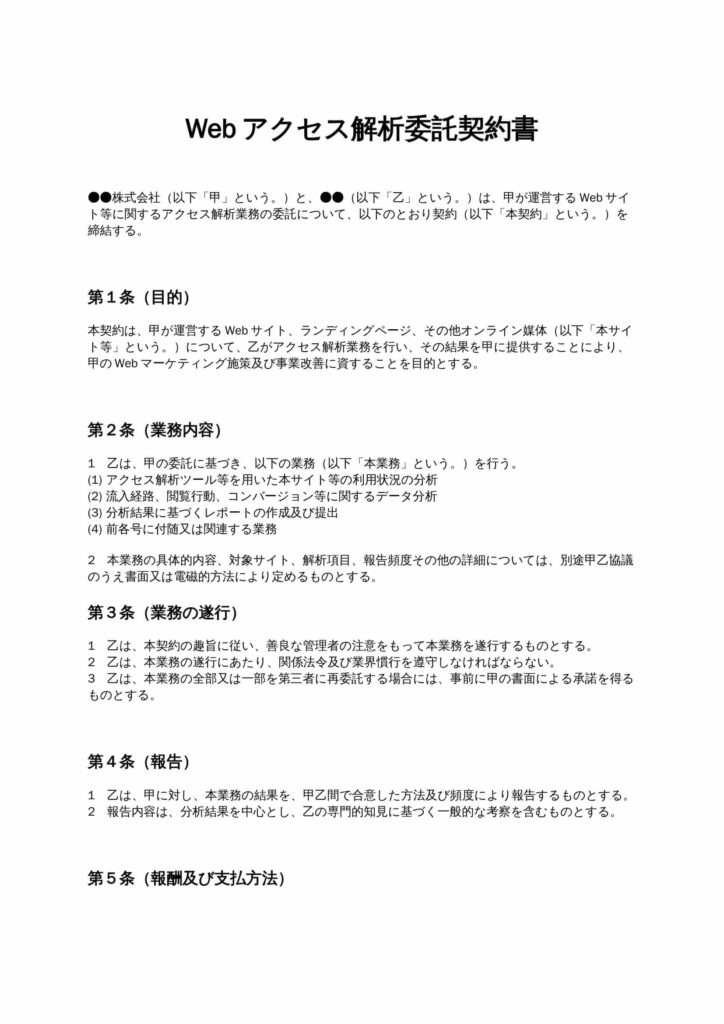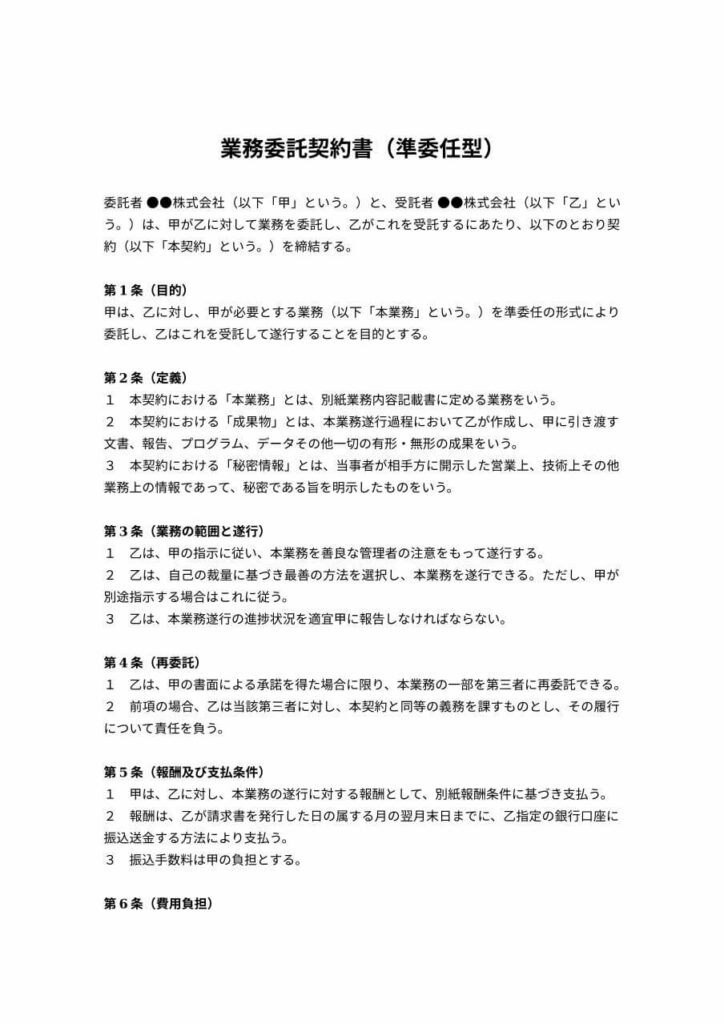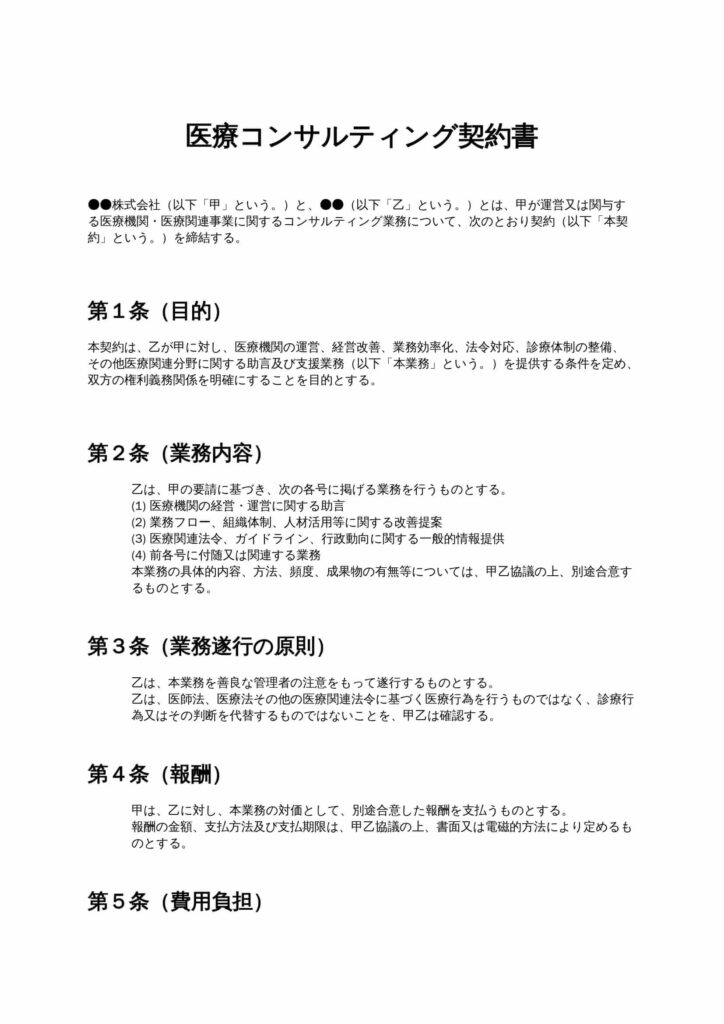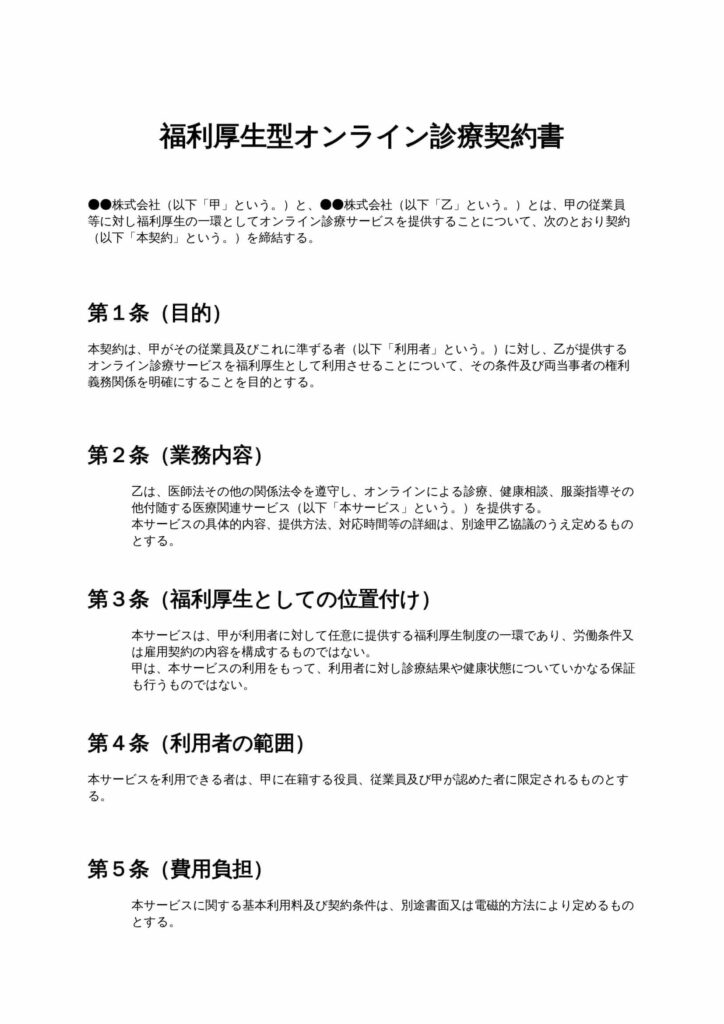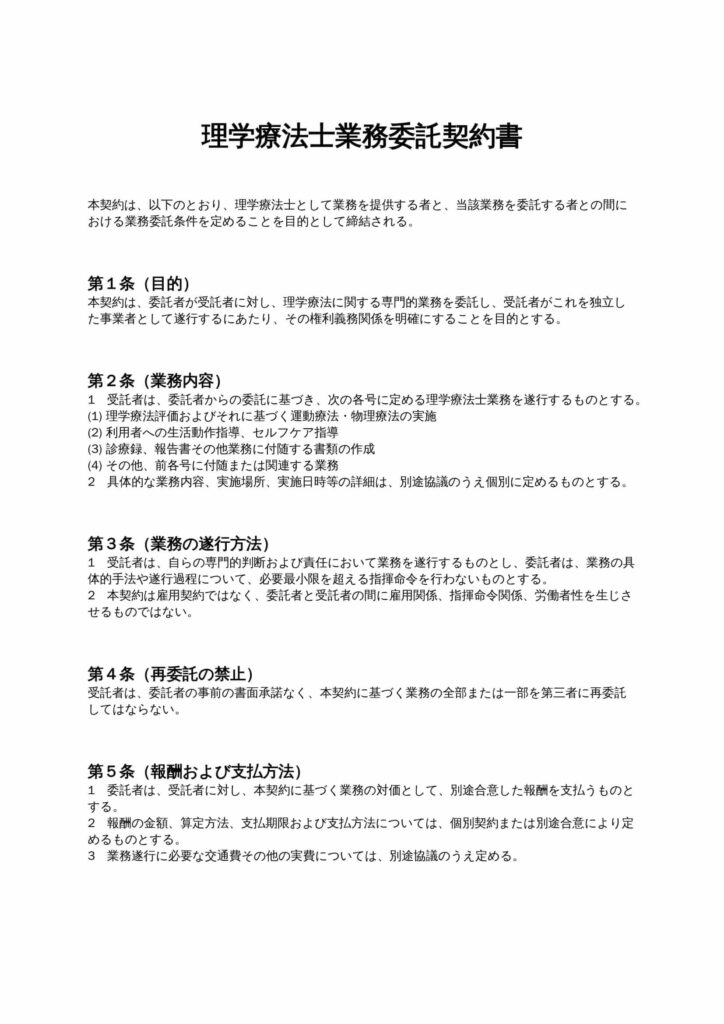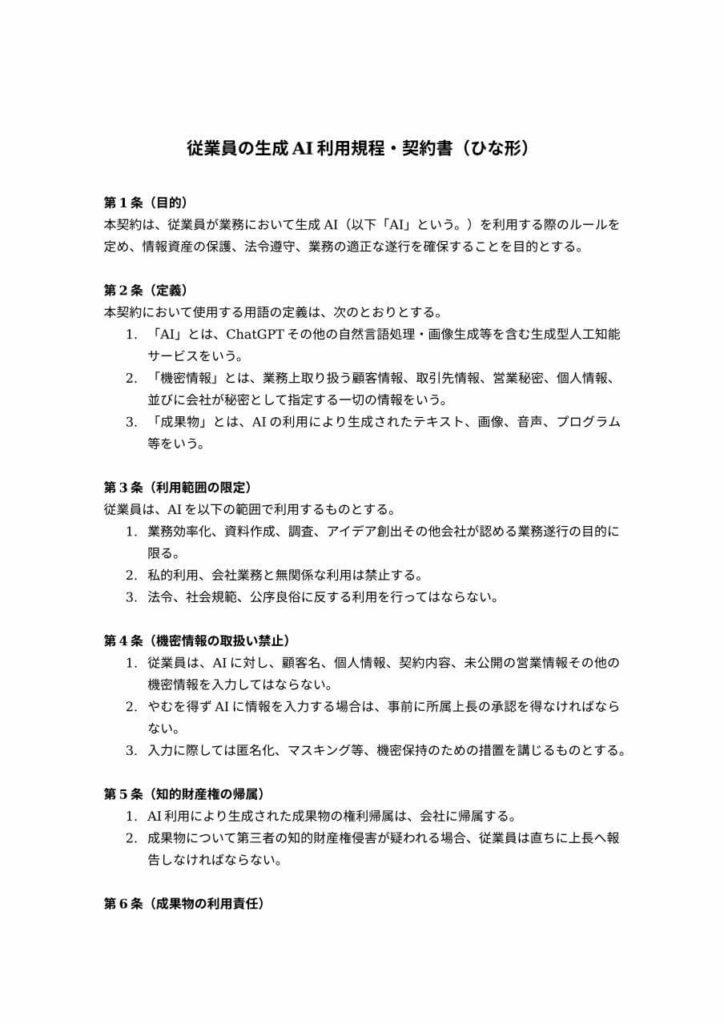業務委託契約書(成果物納品型)とは?
業務委託契約書(成果物納品型)とは、成果物の納品を完了した時点で報酬の支払い義務が発生する契約形態です。労働時間や作業プロセスに基づくものではなく、あくまで完成物の納品が基準となります。請負契約と近い性質を持ちますが、委託する業務の種類や成果物の内容によって柔軟に調整できる点が特徴です。特にITシステム開発、ウェブデザイン、研究調査など、成果物が明確に定義できるプロジェクトに適しています。
業務委託契約書(成果物納品型)が必要となるケース
- システムやアプリケーションの開発を外注する場合
- デザインや映像制作など、完成物を納品する業務を委託する場合
- リサーチやレポート作成など、納品物が契約の中心となる業務
- マーケティング施策に伴う分析・資料作成業務
これらの場合、成果物の完成度や品質が支払い条件の前提となるため、契約書で詳細に取り決めておく必要があります。
業務委託契約書に盛り込むべき主な条項
- 業務内容の定義
- 成果物の納品方法・検収手続き
- 報酬額と支払条件
- 知的財産権の帰属
- 再委託の可否と条件
- 秘密保持条項
- 契約解除条項
- 損害賠償条項
- 準拠法と裁判管轄
条項ごとの解説と注意点
業務内容の明確化
委託内容を曖昧にすると、納品時に「期待していたものと違う」といったトラブルが起こりやすくなります。別紙仕様書を添付し、具体的に成果物の範囲・要件・納期を定めることが重要です。
成果物の納品・検収
納品物を受け取った甲がどのように検収を行い、どの時点で正式に受領するかを明記する必要があります。検収期間や合格基準を明文化しておくことで、納品後の修補や再納品をめぐる争いを防ぐことができます。
報酬と支払条件
支払条件は「納品完了後」に限定されることが多いため、乙の立場ではキャッシュフローに影響が出やすい点に注意が必要です。中間金の設定や分割払いの可否を協議することも実務上有効です。
知的財産権の帰属
成果物に関する著作権や特許などの帰属先を明確にしておかなければ、後に権利関係のトラブルが発生します。原則は委託者(甲)に帰属させつつ、乙が有する既存ノウハウや第三者著作物が含まれる場合は別途取り扱いを明記します。
再委託条件
乙が業務をさらに第三者へ外注する場合のルールを定めます。甲の承諾が必要とするのが一般的ですが、専門性が高い業務では再委託を前提とした柔軟な条項を置く場合もあります。
秘密保持条項
業務遂行中に知り得た営業情報や技術情報を第三者へ漏えいしないよう、守秘義務を定める必要があります。契約終了後も一定期間効力が存続する形とするのが通常です。
契約解除条項
契約違反や倒産などの信用不安が発生した場合に備え、催告なしで解除できる条件を記載しておきます。これにより、重大なリスクが発生した際に速やかに契約を終了できる仕組みとなります。
損害賠償条項
契約違反により損害が生じた場合の責任範囲を明示しておきます。損害額の上限や弁護士費用の負担なども明文化しておくと実務で安心です。
準拠法と裁判管轄
国内契約では日本法を準拠法とし、訴訟が必要となる場合の裁判所を合意しておきます。一般的には委託者(甲)の本店所在地を管轄する地方裁判所が選択されます。
契約書を作成・利用する際の注意点
- 成果物の仕様を曖昧にしないこと
- 検収方法と不適合時の対応を明確にすること
- 報酬支払条件を双方の資金繰りに配慮して定めること
- 知的財産権や秘密保持義務は契約終了後も効力を残すこと
- 不可抗力やトラブル時の協議条項を入れておくこと
これらの観点を押さえておくことで、委託者・受託者双方にとって安心できる契約関係を構築することが可能です。